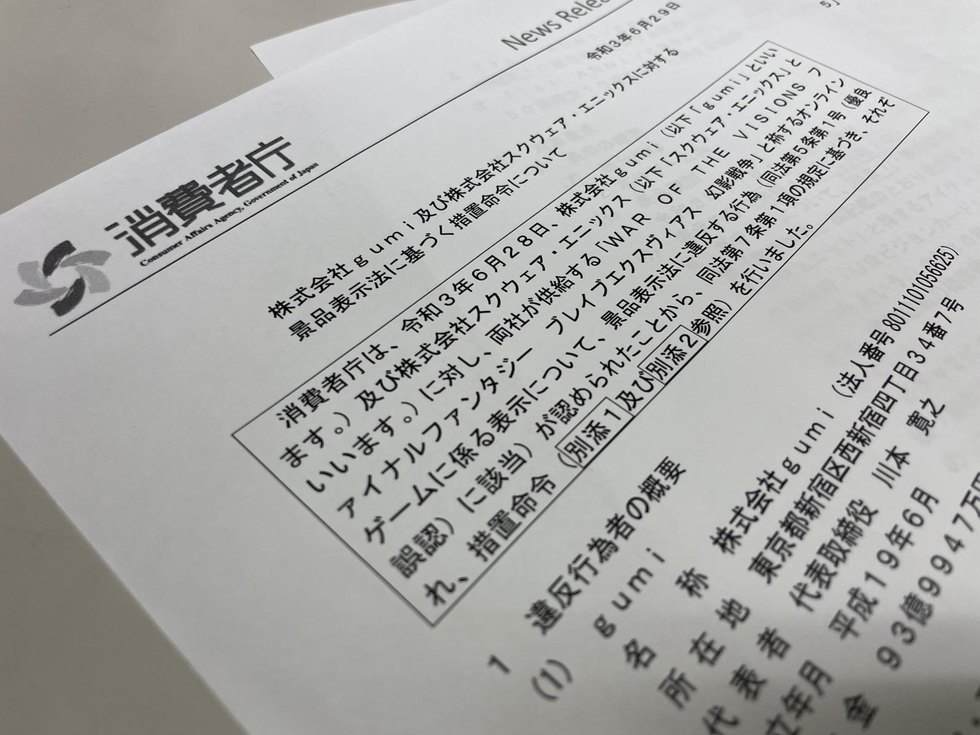新型コロナウイルスによる巣ごもりの影響で活況を呈しているゲーム業界。制作現場はこの状況をどう捉えているのか。ゲーム制作を手掛けてきた「monoAI technology(モノアイテクノロジー)」(神戸市中央区)のXR事業部営業マネージャーの鹿住淳さんに聞いた。
■実は不安だった制作現場
--ゲームはどうやって作られている?
鹿住 多くの場合、ゲームはタイトルを企画して宣伝広報や販売、リリースを中心に行う「パブリッシャー」と、実際にゲームのプログラミングやデザインなどを手がける「デベロッパー」によって制作されます。
「パブリッシャー」は通常、マリオやガンダムなど知名度の高いキャラクターを持っている任天堂やバンダイといった有名企業が多いです。
--コロナによる巣ごもりで、業界は大きな追い風を受けている
鹿住 需要の高まりは確かにあり、特にパブリッシャーの売上が好調です。数倍に増えている企業もあります。デベロッパーという作り手サイドで言うと、ユーザーはコンテンツを消費していくものです。そうなると新しいコンテンツを次々と出さないといけなくなります。コロナ禍の中で制約もあり、業界全体がイケイケという感じではなかったのが実情です。
--一方で、ユーザーは順調に増えている
鹿住 各社ともユーザー離れには相当気を使っています。巣ごもりによる潜在的なユーザーも増えているので、新規顧客獲得のため、アイテムを配ったり、人気キャラクターとのコラボレーションイベント、予定にないフェスを開いたりといった工夫はかなりしました。
というのも、コロナによる社会不安で人々の関心がゲームではないものに持っていかれてしまうのでは、という気持ちが強くありました。コロナに関するニュースにくぎ付けになってしまい、ユーザーが他のメディアに流れてしまう可能性は十分にありました。われわれの商売は時間をいかに使ってもらうか。各社アイデアを出して頑張っていたと思います。
■ゲームのライバルは新聞!?
--ライバル視していたのはニュース?
鹿住 「ユーチューブ」や「TikTok」などは、業界としてはどちらかというと共存していく気持ちが強い。ゲーム実況中継などの動画を流すユーチューバーさんも多く、誘導してくれている側面もあります。スマートフォン(のアプリ)からスマートフォン(のアプリ)は移動しやすい。しかし、テレビなどほかの端末からスマートフォンへというのは難しい。
■ゲーム内でライブを体感
--デジタル化が進んだことも、ゲームの世界と相性がよかった?
鹿住 もともと若い人はスマホを通じて、デジタル空間に自分を投じることが多かったように思います。他社のゲームですが、ユーザーが同時に戦い、誰が生き残るかというバトルロイヤル系の人気ゲーム「フォートナイト」で、2020年8月、大きな話題になったイベントがありました。
ゲームの中で歌手の米津玄師さんがライブを開いたのです(※1)。ゲーム内に登場する大型スクリーンに、同じ世界観の衣装を着た米津さんが映し出されました。
プレイヤーはアバター(分身)として参加します。アバターは米津さんの映像を見ながら、喜怒哀楽を表現することはもちろん、飛んだり跳ねたり、現実にはできないようなアクションもできます。もちろん隣の人に話し掛けることも可能で、現実以上に「レイブ」(野外音楽ライブ)を体感できるという新しい楽しみ方が提供されました。
※1編注:フォートナイトの米津玄師さんライブ予告動画はYouTubeで400万回以上の再生回数を記録した
昔は1対1、5対5で対戦するのがやっとだったのに、今はインフラとハードが進化し、100人が同時にプレイできるゲームが登場しています。コロナ禍の中でも、大勢が集えて楽しめる空間がある。ゲームが培ってきた高い技術力があったからこそ実現できた結果だと思います。
■「ガチャ」ターゲットは30~40代
--ソーシャルゲーム全盛期。課金者も少なくない
鹿住 意外に思われるかもしれませんが、ソーシャルゲームは無課金者が多ければ多いほどいいんです。無課金の人が、課金者に対して、なぜあんなに(ゲーム内で)早く動けるのか、どうしてあんなに強いの?と疑問に思って初めて課金をする。
例えば、子どものころ、欲しかったプラモデルが買えなかったことがあると思います。お小遣いが足りなかったり、商品の在庫がなかったりといった理由があったでしょう。次の世代を育てるためにはそういった経験が必要です。
われわれのゲームは、そういった経験を持った30~40代の可処分所得を持つ層のお客様が一部課金すればもうかるような仕組みになっています。10代は普通に遊んでもらって、ちょっとやられて(やっつけられて)もらえればいいのかなと思います(笑)。
■無課金者が勝てるゲームがヒットの秘訣
--課金者が多過ぎるとゲームバランスが崩壊する?
鹿住 それはどの会社も考えていると思います。課金者が強すぎると、ゲームバランスは簡単に崩壊します。ユーザー層も広がらない。このバランスは本当に微妙なのですが、あるアイテムを装備すると、数%のスピードが上がったり、力が上がったりする。要は無課金の人でも、課金者に勝てるところを作っておくことでゲームのバランスが保っていけるのです。
例えば、じゃんけんで、グーに当たるキャラクターを少し強くする。そうすると次はチョキを強くする。今度はパーの強さも引き上げるといった具合です。一つのゲームが長く愛されていくにはこうしたバランスの配慮が重要になります。
■周回ゲームは生活の一部に組み込んでもらうため
--終わりがないのもソーシャルゲームの特徴。開発側としても長く続く方が望ましい?
鹿住 望ましいですね。キャラクターとのコラボレーションなどをしてユーザーの裾野を広げたとしても、それは大抵、一時的な延命措置。カンフル剤にしかなりません。日ごとにイベントを変え、生活の一部、習慣の中に入れてもらう。ちょこっと触れば、ちょこっとだけ強くなれる。そういうゲームの方が好かれる傾向があります。
朝、通勤や通学の時間帯に少し遊んで、行動できるアクティブポイント(AP)がなくなる。夕方になるとポイントが回復するので、帰り道にまた遊ぶ。ゲームサイクルと、生活のサイクルを一致させていくのです。
毎日のミッションとして同じステージを何度もしてもらう周回ゲームが多いのもこういう理由からです。地味だけど毎日同じ事をしてもらう。その中にイベントとして楽しみを埋め込んでいく。ただ、キャラクターを強くしていくだけだと、自分がどれだけ強くなったか分からない。だからイベントなどを開いて分かってもらうのです。
■ゲーム規制、業界はどう考える?
--依存者が増える中で、業界に規制を課すべきとの議論もある
鹿住 香川県で条例ができましたが、われわれとしては規制の法的根拠などがない限り、制御はできないのではないのでしょうか。
ソーシャルゲームはネットワークで全世界とつながっています。われわれも日本語版だけでなく、英語版や中国語版などを全世界に発信しています。国内のゲームだけ海外版とは異なるプログラムを組むのは非常なコストと手間がかかります。特にゲーム先進国で、膨大なゲームユーザーがいる中国の市場は無視できません。現在はシンガポールやインドネシアなど華僑が多いところで先にリリースして、反応をみて中国への展開を検討しています。
これとは逆に中国や韓国からのゲームも日本に数多く導入されています。これまでは絵柄などが日本と違うこともあり、国内ではあまり普及していませんでしたが、最近は日本に近いイメージのものを作ってきていて脅威です。こうした海外のゲームは国内だけの規制だと縛れないのであまり効果があるとは思えません。
--業界としてどう向き合うべきか
鹿住 活発になっている「eスポーツ」など多くの目を向けられている場所でメッセージとして「健康的なゲームライフ」をアピールしていくのが大事ではないでしょうか。
昔でいうと(ファミコン名人として知られた)高橋名人が「ゲームをやる時間」を子どもたちに注意していたでしょう。スローガン的な訴えをeスポーツなどゲームユーザーが必ず目に触れるところですることが効果的だと考えます。
<モノアイテクノロジー> 神戸市に本社を置くゲーム制作会社。スマートフォンアプリ「Fate/Grand Order Waltz in the MOONLIGHT/LOSTROOM」(グラフィック制作協力)、「勇者のくせにこなまいきだDASH!」(運営協力)などの制作に参画。「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて」の一部背景モデルも制作した。