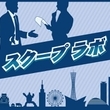テーブルにいつもは見ない花。若いママや中年男性が席を埋める。
毎月第1日曜日、「グループリビングてのひら」(高砂市)の居間では「コミュニティー喫茶」が開かれる。毎回40人ほどが訪れる客のお目当てはランチ。250円とは思えない献立と味の良さだ。
今年3月、てのひらを運営するNPO法人で働く松下愛子さん(73)らが始めた。住人7人も顔を出す。
「あら、久しぶり」。近くの自宅はそのままにして1年前に入居した長岡千代子さん(84)が、同じテーブルについた女性と手を握り合う。
かつてのご近所との再会。「体調どないです?」「ぼちぼちです」。長岡さんは頬を緩めた。「こないして会えたらうれしいねえ」
てのひら近辺は住宅街。「お年寄りが増えて外に出る人が減った。きっかけがあれば集まるんやね」。松下さんは手応えを口にした。
‡
9月、元看護師など女性5人の「サポーターズ」が始動した。毎日1時間半、66~96歳の住人の夕食準備を交代で手伝う。
地元の人に見守ってもらい、住人には地域の一員と感じてほしい。NPO理事長の石原智秋(ちあき)さん(68)が5年前にてのひらを建てた時からの夢だった。毎月の喫茶やサポーターズはその一歩だ。
「寒卵(かんたまご)って知ってます?」。ある日、石原さんが詠んだ歌を見せてもらった。
〈地球上のこの一点の 掌(てのひら)の寒卵割る小さき音たて〉
「鶏が冬に産む栄養いっぱいの卵のことを言うんです」
地球から見ると小さな手のひらの上で、意味のあるものを生み出していきたい-。「てのひら」という名称には、そんな思いが込められていた。
‡
連載を始めてから、てのひらには問い合わせや見学が続いているという。
「空き家を購入し、仲間と一緒に暮らす家にしたい」と姫路市のリタイア後の夫婦。丹波市のNPO法人の男性も相談を持ち掛けた。
「『既製品』では満足できず、老後の居場所を自分なりにつくりたいという人が増えているのでしょう」。高齢者の住まいに詳しい慶応大の大江守之教授は分析する。
法制度に伴い、高齢者向け住宅は急激に増えている。多種多様に見えつつ、費用やサービス面で折り合わないことも多い。「てのひらのような小規模な共同生活は、受け皿になる」と大江教授はみる。
もちろん、すべてを満たすわけではない。見守りなど課題もある。だが、住み慣れた地域を離れずに済み、自由がある。選択肢を広げるヒントにはなるはずだ。
石原さんが大切にする「寒卵」という言葉をかみしめる。人生の玄冬期を豊かなものに。それは、超高齢社会を生きる私たち共通の願いなのだと思う。
(宮本万里子)
◆
「兵庫で、生きる」第3部は今回で終わります。