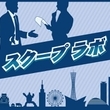地域でそれぞれ確かな存在感を示しながら、今は姿を消した「旧名所」があります。
古くから都市部として発展し、多くの人や物を集めてきた阪神地域はその宝庫です。人気だった娯楽施設や、生活の中のランドマークに加え、先の戦争の記憶も…。
その面影と時代の空気を探して歩きました。(2020年8月の連載から=肩書、年齢は当時)
■労働者運んだ工都の「足」 軍需絶え高度成長で廃線
阪神出屋敷駅の南西に造成された尼崎市の「出屋敷西公園」。800平方メートル足らずの敷地にジャングルジムや滑り台、ブランコが並ぶ。
ただこの公園、南北が異様に細長い。「線路の跡地だからです」。尼崎市立地域研究史料館の西村豪さん(45)が言う。ここにはかつて、阪神・尼崎海岸線が走っていた。
尼崎海岸線は、西宮市の今津駅から南下して出屋敷駅までを結ぶ予定だった「今津出屋敷線」の第1期工事として着手された。1929(昭和4)年4月、本線の出屋敷駅から海岸にほど近い終点の東浜駅まで1・7キロの区間で開業した。
市南部は名産の伝統野菜「尼イモ」の産地だったが、重化学工業の工場が次々と建ち、阪神工業地帯の一角を形成していく。中間駅となる高洲駅の周辺には大勢の労働者が行き交った。阪神電鉄の「80年史」には「乗客の大半は臨海部にあった大谷重工業の工場従業員であり、その通勤輸送に供されていた」とある。
戦争の激化に伴い、企業は軍用製品の受注に追われた。尼崎市神田北通8の吉田敬一さん(88)は、44年から学徒動員で同線を利用した。毎朝混雑する2両編成の電車に乗って高洲駅前の日立製作所尼崎工場に向かい、起重機の製造に明け暮れた。通勤の車窓からはあちこちに町工場が見えたが、「どこで何を作ってるとか、そんな話は絶対したらあかんかった」。厳しい戦時下の統制を振り返る。
最後の乗車日は45年8月15日。事務所前の広場で玉音放送を聞いた。「雑音が多くて何を言うてるか分からず、家に帰ってから負けたことを知った。悲しかったね。だけど、もう空襲がなくなると思うとほっとしたな」。そして遠い目に。
「海岸線の記憶は戦争のこと以外思い出されへんな」
戦中には今津出屋敷線の第2・3期工事の一環として、東西路線の接続が計画されていた。軍需工場が相次いで建設される中、西宮市では43年、武庫川河口近くにあった川西航空機の工場へ貨物や工員を運ぶため、武庫川線が開設した。
さらにそれを尼崎海岸線と接続させるため、武庫川には橋の建設が急ピッチで進められた。だが戦局の激化で、工事は頓挫。橋脚の基礎部分は少なくとも昭和60年代までは残存していたという。
戦後、高洲駅の乗降人員は49年にピークを迎えたが、その後は伸び悩んだ、と尼崎市史は伝える。そこに水害が追い打ちをかけた。50年9月にジェーン台風が発生。沿線の広範囲が浸水し、復旧には2週間以上を要した。南部一帯の地盤沈下も重なり、高洲-東浜間の運行は51年に休止し、60年に廃止された。
さらに高度経済成長期に入ると、モータリゼーションの波が押し寄せた。国道2号の渋滞緩和のため、第二阪神国道(国道43号)の建設案が浮上。その予定地を海岸線が南北に横切るため、同電鉄は62年に高洲駅までの路線を廃止し、輸送はバスに引き継がれた。もともと需要は頭打ちで、「80年史」には「巨費を投じて立体交差にするほどの意味も少ないと考えられた」とつづられている。
かくして線路は姿を消したが、西村さんは調査で発見した痕跡を教えてくれた。出屋敷西公園の北側に打ち込まれた境界杭(くい)。地面から顔をのぞかせた表面は赤く塗られ、阪神電鉄の「阪」の文字が読み取れる。「尼崎海岸線の線路があった名残でしょう」。西村さんは分析する。
背後で高架を走る列車の音がこだまする。戦争をまたいで30年ばかり、市民を運び続けた南北支線。わずか2キロ足らずの線路に、工都の歴史が詰まっていた。(風斗雅博)