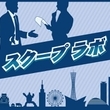スマホをサイレントモードにしてポケットに入れていた学生は教室の外に置いていた学生よりも記憶力や集中力が落ちる-。スマホへの過度な依存が脳に与えるショッキングな影響にあらためて警鐘を鳴らす「スマホ脳」が大きな反響を呼んでいる。スウェーデンで出版され、世界13カ国以上で翻訳、日本語版も22万部を超えるベストセラーとなり、特に子育て世代や女性の関心が高いという。翻訳したのは西宮市出身の久山葉子さん(スウェーデン在住)。「子どもにスマホとどう付き合わせたらいいか、心配している人が多いことの現れだろう」と分析する久山さんに聞いた。
著者は同国の精神科医アンデシュ・ハンセン氏。さまざまな実験を基に、スマホを寝室に置いている子は、そうでない子と比べて睡眠時間が1時間短いといった結果が記されている。
「メールや会員制交流サイト(SNS)で間断なく情報を入れ続けると、情報が記憶に変わるプロセスが妨げられる」など、脳が受けるダメージを解説し、「ひとつのことに集中することが、記憶するためには必要である」と呼び掛ける。
「原書が分かりやすかったので翻訳の苦労はなかった」と話す久山さんだが、「読む前は、自分自身もスマホのせいで集中力や記憶力がだんだん弱っているような気がして、暗い気持ちになっていた」。翻訳作業中はSNSを使えないよう設定すると、「仕事に集中できるようになった」と振り返る。
著者は「スマホは最新のドラッグである」と衝撃的な主張をした上で、自分のスマホ利用時間を把握することや、未成年に対しては一定の制限をかけること、一日数時間は電源を切るなど、具体的な行動を提言する。基本に返り、適度な運動がストレスに有効であることも訴える。
そのアドバイスに習い、ウオーキングを始めると「精神的に強くなった」と久山さん。本の内容を身をもって実感している。
スウェーデンでは「スマホ脳」のジュニア世代版も出版され、注目を集めているといい「これも日本でも出版できる機会をつくりたい」と意気込んでいる。
「スマホ脳」は新潮新書刊・1078円
(井原尚基)
■「スマホ脳」で紹介された研究成果の例
・人々は平均して10分に一度スマホに触れ、一日のうち3時間スマホを使っている
・スマホを熱心に使う人ほどストレスの問題を抱えている場合が多い
・自己評価が低い人は、SNSによって自分を他人と比較しがちになり、精神状態が悪くなるリスクを抱えている
・スマホを長時間使うほど衝動的になりやすく、音楽の演奏技術上達といった将来の「ごほうび」のために我慢することが苦手になる
・眠る前にスマホを使うと、ディスプレーから放たれる青い光の影響で体内時計が2~3時間巻き戻され、時差ぼけが起きたような状態になる
・2~3歳の子がタブレット端末によって何かを学べると考えるのは希望的観測でしかない
■ ■
訳者の久山葉子さんは1975年、西宮市出身。神戸女学院に中学部から大学まで通学した。高校時代、スウェーデンへ1年間留学し、大学卒業後は、日本とスウェーデンの貿易を促すコンサルタントを経験。長女が1歳だった2009年、IT企業に勤める夫が「もっと家族と過ごし、心に余裕のある生活をしたい」と提案し、翌年同国へ移住した。
子育て中の女性が就業することは当然で、入所を希望すれば、保育園の確保が自治体に義務付けられている同国。充実した福祉政策を喜ぶ一方で、「主婦」という概念がないことに新鮮な驚きを感じながら翻訳の仕事を始めた。
「小さなころからイギリスやドイツの児童文学が好きで、ヨーロッパへのあこがれがあった」久山さん。これまでに、日本でも人気の北欧ミステリーを中心に約30冊を翻訳し、19年にはスウェーデンでの育児体験を記したエッセー集「スウェーデンの保育園に待機児童はいない」(東京創元社)も出版した。
現在は現地の高校で日本語教員としても働きながら翻訳に励んでいる。(井原尚基)