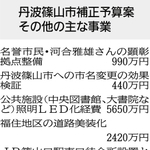日本六古窯(こよう)の一つとして日本遺産に認定された丹波焼の材料「杯土(はいど)」を、30年近く作り続ける職人がいる。原田清さん(71)=兵庫県丹波篠山市=だ。たった1人で守り続けた独自の精製方法は、作品の出来栄えを陰で支えてきた。「丹波焼の命とも言える土を任せてもらってる。窯元たちの生きるもとを作ってるということや」と原田さん。同市今田町上立杭の工場で、土と向き合ってきた自負が透けて見えた。(綱嶋葉名)
原田さんは、畳職人の2代目として働いていたが、同級生の窯元から「杯土工場が人手不足で困ってる。働いてくれないか」と声をかけられた。43歳のときだった。
丹波焼の杯土は元来、それぞれの窯元が作ってきたが、「とにかく手間がかかった」(原田さん)。このため、窯元でつくる「丹波陶磁器協同組合(現丹波立杭陶磁器協同組合)」が1963年、工場を設立。原料土の共同購入と杯土の一括生産が始まった。
原田さんが働き始めたのは、工場ができてから30年後。当時、60代の先輩職人が1人で杯土を作っていた。あいさつをすると、「若いもんが何しにきたんや」とあしらわれた。職人かたぎの先輩がコツを伝授してくれるはずもなく、作業を盗み見て、作り方を学んだ。だが、1年後に先輩は工場を去り、たった1人になった。
苦労したのは「口では説明できない土の絶妙な配合」。丹波焼の杯土は主に、同市弁天などで取れる田んぼの土「奥土」と、同県三田市四ツ辻で調達する「原土」を混ぜて作る。
山から取る原土は、層によって砂や粘土などの質感がバラバラ。それを調整するのが奥土だが、その配合は経験と勘に頼っている。耐火性が弱い奥土を入れすぎると、高温で焼くと割れてしまい、「土の色や手触りなど五感を使って調整している。ずっと作ってると、焼き上がった土の姿がなんとなく浮かんでくるんよ」と話す。
2年前、転機が訪れた。丹波伝統工芸公園「立杭陶(すえ)の郷」(同市今田町上立杭)で陶芸教室のスタッフだった前中郁人さん(30)が工場を訪ねてきた。杯土作りを志願するためだった。
原田さんは当初、「えらい若いもんが来たな」といぶかった。ただ一言「作業は見て覚えよ」とアドバイスした。
一緒に仕事をするうち、黙々と作業に打ち込む前中さんの真面目さにほれ込んだ。今では「息子みたいなもん」と原田さん。杯土作りの要となる土の配合以外の工程は、ほとんど前中さんに任せるようになった。「窯元は命がけで丹波焼を作ってる。安定した土を提供せなあかん」と伝え続けている。
原田さんは「70歳を過ぎて、体力的には大変。でも引き受けたからにはできるところまでやる」と言い切る。納得できるまで打ち込んだ後は、前中さんにバトンを渡すつもりだ。

-
東播三田北播丹波

-
丹波地方行政

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波連載丹波

-
丹波地方行政

-
丹波連載丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波教育高校受験

-
丹波

-
丹波

-
丹波防災

-
丹波スポーツ野球

-
丹波スポーツ野球

-
丹波スポーツ野球

-
丹波

-
丹波

-
丹波野球

-
丹波野球

-
丹波野球

-
丹波野球

-
丹波三田野球

-
丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波教育

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波スポーツ

-
丹波防災

-
丹波

-
丹波

-
但馬丹波三田阪神姫路西播

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波連載丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波医療

-
丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波

-
丹波神戸但馬西播

-
丹波#インスタ

-
丹波かなしきデブ猫ちゃん特集

-
丹波野球スポーツ

-
丹波阪神#インスタ

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波#インスタ

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波

-
丹波連載丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波#インスタ

-
阪神三木北播丹波