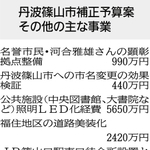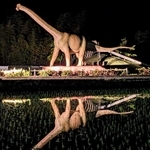兵庫県丹波篠山市の岡野地区で10月、土地の所有者に代わり、地区内の耕作放棄地の雑草を刈る住民グループ「おかの草刈り応援隊」が発足した。本格的な始動を前に、大量に出る刈草の活用法を探ろうとこのほど、岡野文化会館(同市西岡屋)で研修会が開かれた。神戸大学大学院農学研究科の研究者2人が、焼土肥料を作る「灰屋(はんや)」の活用などについて講演した。(真鍋 愛)
農業従事者の高齢化や、耕作放棄地の増加が課題となっている同地区。農業に関する地域の問題を明らかにして解決策を探ろうと、岡野ふるさとづくり協議会は2017年、同協議会内に「岡野の農業を考える会」を設立。課題の一つに挙がった耕作放棄地などの草刈りについて検討を重ね、実践組織として、同グループを立ち上げた。
しかし、活動にあたり、草刈り後に出る刈草の処理が問題となった。廃棄物処理法や環境汚染防止の観点から野焼きはできず、そのまま放置することもできない。そこで、地域に残る灰屋に目を付けた。
灰屋は土壁で囲われた、簡素な造りの小屋で、「灰小屋(はいごや)」とも呼ばれる。刈草や豆殻などを土と重ねて燃やし、焼土肥料を作る施設で、かつては市内各地で見られた。焼土肥料は黒大豆などの生産に使われたといい、市などが日本農業遺産の認定を目指して今年申請した「丹波篠山の黒大豆栽培~ムラが支える優良種子と家族農業~」でも、遺産価値を構成する要素の一つとして挙げられている。
研修会で、同研究科の清水夏樹特命准教授=農村計画学=は「農業を続けるために草刈りが必要になり、刈草を利用したいという思いが生まれる。継続的な農業の営みがあるからこそ、灰屋の文化財的、環境的、産業的価値は生まれる」と語り、「灰屋をただ保存するだけでは意味がない」と指摘した。
鈴木武志助教=土壌化学=は、11年に市内の農場で行われた、焼土を使った「丹波黒」の栽培実験や、畑に敷いた草と豆殻に土をかぶせて火を付ける、省力的な焼土の作成法を検証した実験を紹介。「焼土は灰屋で作る労力の割に、肥料成分が少ない」とする一方で、「市内のほ場は肥料が多く含まれ、成分効果の試験に向かない。耕作放棄地を使った実験を行うべき」と、より正確な実験の必要性に言及した。
同グループ代表の谷田又次(ゆうじ)さん(72)=同市=は「『焼土は黒大豆の肥料になる』といった明確な答えは出なかったが、地域に残った灰屋を活用した、循環型農業のあり方について考えたい」と話した。

-
東播三田北播丹波

-
丹波地方行政

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波連載丹波

-
丹波地方行政

-
丹波連載丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波教育高校受験

-
丹波

-
丹波

-
丹波防災

-
丹波スポーツ野球

-
丹波スポーツ野球

-
丹波スポーツ野球

-
丹波

-
丹波

-
丹波野球

-
丹波野球

-
丹波野球

-
丹波野球

-
丹波三田野球

-
丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波教育

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波スポーツ

-
丹波防災

-
丹波

-
丹波

-
但馬丹波三田阪神姫路西播

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波連載丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波医療

-
丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波

-
丹波神戸但馬西播

-
丹波#インスタ

-
丹波かなしきデブ猫ちゃん特集

-
丹波野球スポーツ

-
丹波阪神#インスタ

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波#インスタ

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波

-
丹波連載丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波#インスタ

-
阪神三木北播丹波