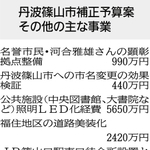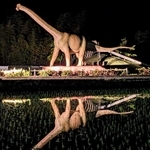山里の耕作放棄地を活用し、ニシキゴイを養殖する事業に、兵庫県丹波篠山市北新町の農業法人「YAGATE(やがて)」が取り組んでいる。地域課題の解決と農業を組み合わせた新しいビジネスモデルづくりの一環。目指すは「持続可能な理想郷」の実現だ。「コイを地元の名産にしたい」とも意気込む。(堀井正純)
「やがて」は、丹波篠山へ移り住んだ黒瀬啓介さん(42)、中島武史さん(53)の2人が2019年に設立。有機農法による黒豆や米づくり、食用のバラ栽培が主な事業で、養蜂も手掛ける。
ニシキゴイの養殖は2年前に着手。山あいにある同市殿町で、地元の農家などから借りた耕作放棄地約35アールを重機で整地し、養殖用の池に転用した。京都府綾部市の養鯉家から指導やアドバイスを受け、稚魚を放して育てている。冬場は寒さをしのぐため、近くの農業ハウス内に設けたプールへコイを移し、飼育している。
「長年放置され、荒れた山際の耕作放棄地を再び農地に戻すのには大変な費用や手間がかかる。養殖池にする方がまだ簡単」と黒瀬さん。「ニシキゴイは日本の庭園文化に欠かせない。農地を活用でき、伝統的な文化の継承にもなる」とメリットを語る。
ニシキゴイは、江戸時代、食用のマゴイの突然変異が新潟の旧山古志村で見つかり、観賞用に育てられたのが発祥とされ、元々、山間部の休耕田や棚池を養殖に用いた歴史がある。黒瀬さんによると、丹波地域でも、昔は水田でコイを飼い、食用にした風習・文化があったという。
ニシキゴイは「泳ぐ宝石」とも呼ばれ、海外でも人気が高く、色や模様の美しいコイは驚くほど高値で取引される。「養殖技術を磨いて、将来的には輸出を目指す」と中島さん。3月中旬に、初めての観賞・販売会を同市殿町の農業ハウス内で開き、約600匹を披露。京阪神からの愛好家らでにぎわった。
今年は、さらに約40アールの耕作放棄地を池へ転用予定。2人は「観賞・販売会は年2回くらい開きたい。養鯉事業も含め、山からため池、水田へと一貫して、生物多様性に富んだ里山の再生に取り組んでいきたい」と話している。

-
東播三田北播丹波

-
丹波地方行政

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波連載丹波

-
丹波地方行政

-
丹波連載丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波教育高校受験

-
丹波

-
丹波

-
丹波防災

-
丹波スポーツ野球

-
丹波スポーツ野球

-
丹波スポーツ野球

-
丹波

-
丹波

-
丹波野球

-
丹波野球

-
丹波野球

-
丹波野球

-
丹波三田野球

-
丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波教育

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波スポーツ

-
丹波防災

-
丹波

-
丹波

-
但馬丹波三田阪神姫路西播

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波連載丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波医療

-
丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波

-
丹波神戸但馬西播

-
丹波#インスタ

-
丹波かなしきデブ猫ちゃん特集

-
丹波野球スポーツ

-
丹波阪神#インスタ

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波#インスタ

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波

-
丹波連載丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波#インスタ

-
阪神三木北播丹波