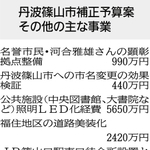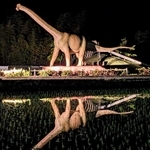甚大な被害をもたらした東日本大震災から11日で12年。兵庫県丹波篠山市を拠点に「ローカルコーディネーター」として活躍する田林信哉さん(39)は、総務省からの出向で震災後の福島県南相馬市副市長を2年間務めた。ゼロから新しい町をつくるため、平日休日問わず現場へ足を運び、人々の話に耳を傾けた。その姿勢は被災地から遠く離れたこの地でも同じ。「南相馬での経験は、間違いなく僕の原点」と語る。
■住民呼び戻すため、遠隔診療や起業支援
着任した2016年4月、南相馬市では道路などの土木工事は落ち着き、依然、福島第1原発事故の影響で避難指示区域に指定されていた小高地区の避難解除について話し合われていた。賠償金の問題が関わることもあり、一部住民からは「解除は早い」という声も出ていたが、震災から5年、「できるだけ早く町を前に進めていかなければならない」という当時の市長らの思いなどから、その夏に解除された。
「いかに避難者に戻ってきてもらうか」。副市長として最重要課題だった。生活に不可欠な医療現場での人材不足解消のため、オンライン診療などを手がける医療ベンチャー企業に協力を依頼し、早くから遠隔診療に挑戦した。津波で更地となった広大な土地をロボットのテストフィールドとして整備し、起業型地域おこし協力隊制度を立ち上げるなど新たな人材の呼び込みにも力を入れた。
震災発生時、田林さんは山口県下関市にいた。当時の南相馬を知らないからこそ、知ることに時間を割いた。すると、住民同士や地域と行政など、互いにコミュニケーションが取れていないことが分かってきた。市役所の職員でさえ「復興」のあり方に納得できていない人がいた。「自分の知らないところで物事が決まり、変わっていく。そういう不安が募ると、先入観で非難してしまうことがある」(田林さん)
■「120%で話を聞く」姿勢貫く
お互いの思いを共有し合うため、集まって話す場を積極的に設けた。田林さんは「課題はすぐに解決しない。でも、みんなで手を取り合って、少しずつ前に進めているというプロセスが大事」と説明する。現場で話を聞き続けることで見えてきたものがある。
「地域で自分が公平に扱われ、意見を言う場があり、認めてくれる人がいるという、その地に住む『満足度』や『誇り』を高める環境づくりが一人一人の幸せにつながる」
地域の特色や、アイデンティティーでもある歴史文化などをいかした地域活性に興味を持ち、20年に総務省を退職した。古民家再生などによるまちづくり事業を手がける「NOTE」(丹波篠山市)で1年働き、さらに地域と密着した活動を求め、21年からフリーで公民連携支援や地域資源の磨き上げなどに奔走する。復興と地域活性。一見違うようにも思えるが「本質は同じ」。地域に根ざした、地域住民のニーズにあった施策を講じていくことが重要という。そのために「120%で当事者の話を聞く」ことを心がける。
南相馬を離れて5年。「心の中に常に存在がある」と田林さん。たくさんの経験を通し、自分を成長させてくれた場所だからこそ強く思いを寄せる。「またいつか貢献したい」
【たばやし・しんや】1983年、和歌山県生まれ。2005年に早稲田大学法学部を卒業後、総務省に入省。山口県庁や内閣府への出向を経て、16年4月から18年3月まで、南相馬市副市長として被災地の復興に従事した。

-
東播三田北播丹波

-
丹波地方行政

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波連載丹波

-
丹波地方行政

-
丹波連載丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波教育高校受験

-
丹波

-
丹波

-
丹波防災

-
丹波スポーツ野球

-
丹波スポーツ野球

-
丹波スポーツ野球

-
丹波

-
丹波

-
丹波野球

-
丹波野球

-
丹波野球

-
丹波野球

-
丹波三田野球

-
丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波教育

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波スポーツ

-
丹波防災

-
丹波

-
丹波

-
但馬丹波三田阪神姫路西播

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波連載丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波医療

-
丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波

-
丹波神戸但馬西播

-
丹波#インスタ

-
丹波かなしきデブ猫ちゃん特集

-
丹波野球スポーツ

-
丹波阪神#インスタ

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波#インスタ

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波地方行政

-
丹波

-
丹波

-
丹波連載丹波

-
丹波

-
丹波

-
丹波#インスタ

-
阪神三木北播丹波