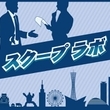ゆるやかな上り坂の北端には六甲の山並みがそびえ、南へ下るとすぐ海に出る。
北野と旧居留地を結ぶトアロードは、神戸港開港以来、多くの外国人が行き交った。「山と海が近い」神戸らしさが凝縮された通り。高級服飾店や総菜店、輸入雑貨店などが「ハイカラ」を体現してきた。
それが、今-。
‡
「過去のことより、これからのことを」
進行役が口火を切った。
今年1月21日、トアロードの会議室にビルのオーナーや商店主ら19人が顔をそろえた。活性化を考えるワークショップの初回だ。
神戸市が行った商業地等実態調査からは、トアロードの厳しい現実が浮かび上がる。日曜日の通行量は1991年で4万256人、2011年は2万1908人。この20年でほぼ半減している。
阪神・淡路大震災で壊滅状態になった一帯の復興を目指し、1996年に組織された「トアロード地区まちづくり協議会」の危機感は強くなる一方だ。
「トアロードは今、本当に死んでいる」。過激な発言にも出席者は一様にうなずく。このまま「普通の通り」になっては名が廃る。「らしさを取り戻さなくては」「花や緑をもっと増やそう」。会議は熱を帯びていった。
‡
「商店街に必要なポイントは、空間の雰囲気、良い店、サービスの3点。これがそろえば人は来るんです」
地域再生や景観まちづくりの専門家として、同協議会の発足時から携わる立命館大客員教授の高田昇(すすむ)さんは断言する。20年かけて、土台はつくったつもりだ。
「トアロードにはまだ可能性がある。手を打つなら、今」
老舗は現状をどう見ているのだろう。婦人帽専門店「マキシン」を訪ねた。昭和20~30年代から、ショーウインドーで復活祭(イースター)など欧米文化を紹介。一帯の、ひいては神戸のイメージを決定づけてきた名店だ。
「ハイカラの原点がマキシンであり、トアロード」。社長の渡辺百合さん(70)の言葉に強烈なプライドがにじむ。「来てもらうにはどうすればいいか考えるいい機会よ」。営業統括部長の柳憲司さん(46)も燃えていた。「何もしなかったら寂れていくだけ。誰かではなく、自分たちが動かないと」
同協議会事務局長の村上恵子さん(56)は震災後、商店主らが一致団結して協議会を組織したときの「すごいパワー」が忘れられない。通り全体を巻き込んで、今こそあの熱気を、一体感を。
三宮、元町かいわい。神戸のど真ん中で生きる人々が、同時多発的に動き始めた。殻を打ち破ろう。新しいことをやってやろう。旅立ちの汽笛は、高らかに鳴っている。(黒川裕生)
◆
「兵庫で、生きる」第6部は終わります。同シリーズを締めくくるエピローグを近く掲載します。