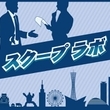暖かみのある淡いオレンジ色の外観。玄関を入ると木の香りが漂う。2007年の新潟県中越沖地震で、自宅が全壊した柏崎市の植木伸明さん(57)が再建した住宅だ=写真。
2階建て約90平方メートル。家族5人で暮らす。「建物本体は800万円ほどで済んだ。あのNPOのおかげです」と植木さん。
「あのNPO」とは「全国防災・災害支援ネットワーク会議(全防災)」。故郷(ふるさと)プロジェクトと銘打ち、「550万円で45平方メートル」を基本に低予算で住宅を建て、被災者の住宅再建を支援する。これまでに10戸を完成させた。
NPOだから利益は求めない。水回りの設備や建具もメーカーから格安で提供を受けた。さらに同年、改正された一つの法律が、取り組みを後押しした。
阪神・淡路大震災を機に制定された被災者生活再建支援法。改正で、最大300万円の支援金を、住宅本体の再建費にも充てることが可能になった。
これに義援金などを加えると、全壊世帯には最大650万円が支給される。「だから550万円なんです」と全防災代表理事の羽鳥大成さん(48)。家を再建し、残った100万で家財などをそろえ、すぐに生活を始めてもらう-との計算だ。
◆
支援法は、再建支援の幅を確実に広げた。同じ07年の石川県能登半島地震でも威力は発揮された。
同地震では、「耐震・耐雪」「県産材の使用」など、再建の際に一定の条件を満たせば県が最大200万円を補助した。法の支援金などを加えると最大で770万円。通常規模の住宅なら費用の半分は賄えた。
法改正は地震後。だが、さかのぼっての適用が決まると、すぐに効果が出た。最も被害が大きかった輪島市。仮設入居者のうち、当初は78世帯が公営住宅を希望していた。しかし改正後、29世帯が自力再建に変更し、元の地域に戻った。
「人口減が不安だったが、どうにか食い止められた」と、石川県の復興担当者は今も口にする。
◆
全防災が取り組む「550万円住宅」は、低価格自体が目的ではない。あくまで地域での自宅再建支援。それも、住まいの再建から取り残されがちな層の支援だ。それが「生活復興の基本」と羽鳥さんは考える。
融資を受けられない高齢者、母子家庭、障害者のいる家庭…。柏崎市からこうした被災者の紹介を受け、取り組みを展開した。
植木さんもその一人だった。歩行が困難になった母親を介護するため、仕事をやめた直後、地震に遭った。仮設住宅に入り再建費用を見積もってもらったが、2000万円以上。駐車場を兼ねた物置に暮らすことも、本気で考えた。
そんなとき、全防災の住宅相談会でその活動を知った。完成した住宅のトイレには、ドアが2カ所ある。一つはリビング側。もう一つは母親の部屋にある。被災者に寄り添い、設計にもこだわった証しだ。
地震後、植木さんに待望の長男(1)が生まれた。「これで地域の子どもが1人増えたことになる」と羽鳥さん。元の場所での住宅再建の大切さは、そんなところにもある。(田中陽一)