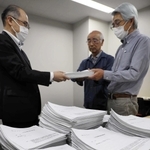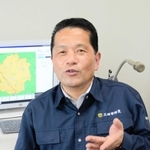2020年1月下旬、春節祭が始まろうとした直前に、中国の旅行者からキャンセルの通知が増えてきました。新型コロナウイルス感染症の始まりだったのです。あれから1年が過ぎましたが勢いは衰えていません。兵庫県の有馬温泉でもたくさんの行事を中止したり、縮小したりしました。
毎年1月2日の「入初式(いりぞめしき)」もその一つ。今年は規模を大幅に縮小し、関係者だけで執り行いました。有馬温泉が恩人とあがめる「行基」と「仁西(にんさい)」の両上人に新年の初湯に入っていただくという儀式です。
そこで今回は、有馬の歴史を海外の旅行者にどうお伝えするかという話です。
行基といえば奈良の大仏を造ったことで有名ですが、その理由はあまり知られていません。奈良時代の735年~738年、天然痘が猛威を振るいました。それが、大仏を造るきっかけとなったのです。
それまでなかった疫病が流行したのは、日本が外国と交流を始めたことが引き金でした。日本書紀によると630年、舒明天皇が初めて遣唐使を派遣します。唐の先進的な技術や政治制度を収集するためでした。
舒明天皇が有馬温泉に来られたのは、その翌年の631年になります。
さらに約20年後の653年には2回目の遣唐使として、堺生まれの「道昭(どうしょう)」という僧侶が選ばれます。道昭は唐の都で「玄奘三蔵(げんじょうさんぞう)」という僧に大変かわいがられたといいます。玄奘三蔵は仏教を研究するには原典を調べる必要があるとして、インドのナーランダ大学から657部の経典を長安に持ち帰った人物です。
この旅の報告書が「大唐西域記」。これは孫悟空で知られる「西遊記」のモデルになったものです。
そして、玄奘三蔵がサンスクリット語の経典を中国語に訳したのが「大般若経(だいはんにゃきょう)」。それを要約したのが「般若心経」です。
玄奘三蔵から学んだ道昭は帰国後、経典を日本国内に広めます。内容は非常に難解なのですが、ある時、15歳の少年が一度読んだだけで理解したといいます。
その少年こそが行基です。その行基が開いたのが有馬温泉なのです。
このような説明を中国人の旅行者にすると、大変興味を持っていただけます。インバウンドを推進するには物語を伝えることが重要で、特にその国と日本、有馬のつながりを話すと喜ばれます。
いつの時代も革新派と保守派の対立があります。もし舒明天皇が海外の先進的な物事を取り入れずに島国に閉じこもっていたとしたら疫病は防げたのでしょうか。いやいや、スペイン人が南米のインディオを支配した末に、持ち込んだ感染症がアステカ王国を滅ぼしたように、日本もどうなっていたかは分かりません。(有馬温泉観光協会)

-
東播三田北播丹波

-
三田阪神

-
三田

-
三田地方行政

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田地方行政教育

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田選挙地方行政神戸

-
三田選挙

-
文化フェス主義!三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田地方行政

-
三田

-
三田地方行政

-
三田

-
三田スポーツ

-
三田

-
三田

-
三田

-
選挙三田

-
三田

-
丹波三田野球

-
三田連載三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田選挙

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田連載三田

-
三田地方行政選挙

-
三田選挙

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田地方行政

-
但馬丹波三田阪神姫路西播

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田選挙

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田スポーツ

-
三田連載三田

-
三田地方行政

-
三田地方行政

-
三田地方行政

-
三田地方行政

-
三田

-
東播三木三田

-
三田神戸

-
三田連載三田

-
三田

-
三田文化

-
三田地方行政

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田地方行政

-
三田

-
三田選挙

-
三田

-
三田

-
三田連載三田

-
三田文化

-
三田地方行政

-
三田

-
三田地方行政阪神

-
三田地方行政

-
三田教育

-
三田連載三田

-
三田

-
三田地方行政

-
三田地方行政

-
三田

-
三田

-
三田地方行政

-
三田地方行政

-
三田地方行政

-
三田神戸

-
三田地方行政

-
三田