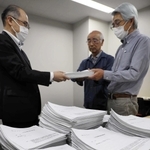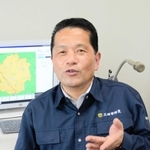自然科学をテーマに最新の研究を紹介する企画展「ひとはく研究員展」が兵庫県三田市弥生が丘6の県立人と自然の博物館(ひとはく)で開かれている。研究員31人がそれぞれの調査、研究をまとめたパネルや資料を展示。化石や動植物の標本も並べ、自然科学に関する研究を論文よりも分かりやすい形で伝えようと工夫をしている。その一端を紹介する。(小森有喜)
■神社と防災の意外な関係(高田知紀主任研究員)
神社に目を凝らすと、意外な発見がある。数百年、数千年もの間、存在できたのはなぜか。さまざまな災害を経験しているため、現存する多くの神社が津波や洪水に対して安全な場所にあるのだ。実際に和歌山県内で南海トラフ巨大地震による津波のリスクを検証すると、9割の神社が被害を受けないというシミュレーションの結果になった。
■外来性フジツボの分布(頼末武史主任研究員)
岩礁に付着する「フジツボ」。実はタンカーの船底にくっついたり、積載する海水に混入したりして、外来種が世界各地に広がっている。侵入先でどんな分布をしているのかを明らかにし、今後はフジツボ以外の海産物にも対象を広げる。
■「異常巻き」のアンモナイト(生野賢司研究員)
アンモナイトには殻の螺旋(らせん)が解けたような「異常巻き」が見られる。調べると、長い棒が折りたたまれたような変な形まである。これは「ポリプティコセラス属」と呼ばれる種類だが、現状では分類が細かすぎる可能性がある。状態のいい化石を観察して見極める。形の違いは個体差なのか時代か、はたまた地域差か。
■生物進化の数理モデル(京極大助研究員)
雄と雌が子どもをつくる「有性生殖」は生き物の生活スタイルや、姿かたちにどう影響を与えるのかを解明する。数理モデルを駆使し、最大2万世代もの未来まで生物のサイクルをシミュレーション。例えば種類の似ているチョウが誤った交雑を防ぐため、配偶相手の好みや、すむ場所をどう変えていくか。
■アリに擬態するクモ(山崎健史主任研究員)
クモ類の中で最も種類が多い「ハエトリグモ類」は奥が深い。脚を触角のように見せかけてアリに擬態(ぎたい)したり、植物由来の餌を食べたりする種類もいる。なぜそんなに多様性が広がり、維持されるのかを研究している。
■絶滅危惧種の遺伝子汚染(中濱直之研究員)
その地ならではの植物を、人が別の場所で植えるなどして遺伝子構造が変わってしまう。これを「遺伝子汚染」と呼ぶ。県内各地の湿地で植生する希少種の「サギソウ」を調べると、これらも別の場所にあった栽培株を植えられた可能性が浮かび上がってきた。
■企業による農業、農地集積への課題(衛藤彬史研究員)
農家が耕作を放棄した田畑をどう管理していくか。その一つに、企業の参入促進がある。国家戦略特区に指定されている兵庫県養父市に参入した企業にヒアリングするなどして、誘致から農業の担い手づくり、そして地域で管理できる体制ができるまでを考える。
◇
展示会を担当する加藤茂弘主任研究員(60)は「ひとはくは来年で30周年。研究員の世代交代も進んでおり、若手の研究にも注目してほしい」と話している。
午前10時~午後5時。月曜休館(月曜が祝日の場合は火曜休館)。大人200円、大学生150円、70歳以上100円、高校生以下無料。4月18日まで。同館TEL079・559・2001

-
東播三田北播丹波

-
三田阪神

-
三田

-
三田地方行政

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田地方行政教育

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田選挙地方行政神戸

-
三田選挙

-
文化フェス主義!三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田地方行政

-
三田

-
三田地方行政

-
三田

-
三田スポーツ

-
三田

-
三田

-
三田

-
選挙三田

-
三田

-
丹波三田野球

-
三田連載三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田選挙

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田連載三田

-
三田地方行政選挙

-
三田選挙

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田地方行政

-
但馬丹波三田阪神姫路西播

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田選挙

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田スポーツ

-
三田連載三田

-
三田地方行政

-
三田地方行政

-
三田地方行政

-
三田地方行政

-
三田

-
東播三木三田

-
三田神戸

-
三田連載三田

-
三田

-
三田文化

-
三田地方行政

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田地方行政

-
三田

-
三田選挙

-
三田

-
三田

-
三田連載三田

-
三田文化

-
三田地方行政

-
三田

-
三田地方行政阪神

-
三田地方行政

-
三田教育

-
三田連載三田

-
三田

-
三田地方行政

-
三田地方行政

-
三田

-
三田

-
三田地方行政

-
三田地方行政

-
三田地方行政

-
三田神戸

-
三田地方行政

-
三田