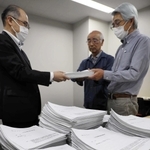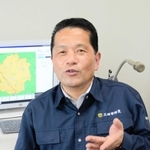■八木剛主任研究員
虫には大きく分けて三つの区分があります。害虫、益虫、ただの虫、です。農業生産や生活衛生に被害を及ぼす虫が害虫、害虫をやっつける虫や植物の受粉を助ける虫が益虫です。人間の都合による区分なので、その判断は人によって違います。「この虫は害虫ですか?」と質問されることは、近年めっきり少なくなりました。
入れ替わるようによくきかれるのは「この虫は外来種ですか?」です。「はい、そうです」と答えると、返ってくるのが「危なくないのですか? 駆除しなくていいのですか?」という反応です。外来生物は害をもたらす、駆除すべきだ、という認識が浸透していることに驚かされます。もはや社会現象といえるのではないでしょうか。
2005年に施行された外来生物法では、人に被害を及ぼす種だけではなく、生物多様性保全の観点から、在来種の生息を脅かす侵略的外来生物や、在来の個体との交雑によって遺伝子汚染を引き起こす外来種を「特定外来生物」として国が指定します。以後、外来種による被害を未然に防ぎ、拡大を防ぐための規制や防除がなされるようになりました。
この法律は画期的なものですが、その趣旨が正しく社会に浸透しているかといえば大いに疑問があります。むしろ誤解が拡散しているのではないかと危惧します。規制や防除の対象は少数の外来種であるにもかかわらず、すべての外来生物が性悪だと思い込む人が少なくありません。外国産品が必ず国産品を駆逐するのではないように、すべての外来生物が危険なわけではありません。
むしろ多文化共生社会のごとく、多くの外来生物はわが国の自然界で在来種と共存しています。しかし、そのような事実はあまり発信されていません。害虫に対して益虫という用語があったように、長く定住している侵略的でない外来生物に対して、たとえば「穏健外来生物」や「共存外来生物」といった呼称が必要ではないでしょうか。外国から来たイコール侵略的と誤解されるのは、そうでない種に対応する呼称がないことも一つの要因だと思います。かつては、帰化生物という用語がよく使われていました。そこには、定住者として受け入れるという意味合いが含まれていたと思います。「侵略的」や遺伝子「汚染」といった排外主義的な表現は、人間に対してではないにせよ、慎重に使用すべきでしょう。
また、外来種の駆除は目的ではありません。農業生産を守り生物多様性を確保するための手段です。生物多様性の保全は持続可能な社会を実現するための手段です。手段と目的を取り違えず、何を守り、未来にどんな景色を望むのか、とくに次世代を担う子どもたちに正しく伝えていくことが、今の大人に求められる使命だと思います。

-
東播三田北播丹波

-
三田阪神

-
三田

-
三田地方行政

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田地方行政教育

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田選挙地方行政神戸

-
三田選挙

-
文化フェス主義!三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田地方行政

-
三田

-
三田地方行政

-
三田

-
三田スポーツ

-
三田

-
三田

-
三田

-
選挙三田

-
三田

-
丹波三田野球

-
三田連載三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田選挙

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田連載三田

-
三田地方行政選挙

-
三田選挙

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田地方行政

-
但馬丹波三田阪神姫路西播

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田選挙

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田スポーツ

-
三田連載三田

-
三田地方行政

-
三田地方行政

-
三田地方行政

-
三田地方行政

-
三田

-
東播三木三田

-
三田神戸

-
三田連載三田

-
三田

-
三田文化

-
三田地方行政

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田地方行政

-
三田

-
三田選挙

-
三田

-
三田

-
三田連載三田

-
三田文化

-
三田地方行政

-
三田

-
三田地方行政阪神

-
三田地方行政

-
三田教育

-
三田連載三田

-
三田

-
三田地方行政

-
三田地方行政

-
三田

-
三田

-
三田地方行政

-
三田地方行政

-
三田地方行政

-
三田神戸

-
三田地方行政

-
三田