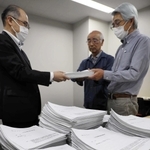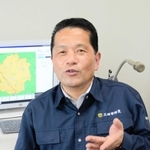■三橋弘宗主任研究員
「これからの時代は外来生物と共生だ!」。最近では専門家や役所の幹部でさえ、無責任な発言が各地でまん延しています。外来生物には、産業利用される有用な種や生活や生態系に影響が小さな種もいますが、深刻な影響を与える種は少なくありません。それに影響が未知の種が大半です。「共生」といった心地良いフレーズを唱えれば、煩わしい駆除の手間が省けるので便利な主張ですが、予防と駆除なくして問題は解決しません。放置すると経済被害を助長します。
昨年、兵庫県では二つの大きな事案がありました。伊丹空港周辺でのアルゼンチンアリの大繁殖、そして明石市、芦屋市、神戸市でのクビアカツヤカミキリの侵入です。伊丹市でのアルゼンチンアリ被害は深刻で、アンケート調査ではまん延地域の約7割の家庭で生活被害、約2割で睡眠障害が発生、電気機器内に侵入し、防犯機器やエアコン室外機が故障するケースもありました。伊丹市昆虫館など関係者の適切な努力で拡散は抑制されて、現在は低密度化が図られています。
一方で、クビアカツヤカミキリは、桜や桃の樹を食い荒らして枯死させます。繁殖力が旺盛で、放置すると学校や公園、寺社の桜を大量伐採することになります。実際に他府県では桜の大量伐採、桃園の廃業など被害は深刻です。県内では明石市や芦屋市をはじめ、県庁や樹木医会や明石北高校とも協働し、問題箇所の対策はほぼ完了しています。が、油断はできません。
この二つの外来生物の侵入に備えて、事前から県環境部を中心に各部局、県自然保護協会、ひょうご環境創造協会などの関係機関で対策準備や技術講習会を進めていました。その結果がスムーズな初期対応に繋がっています。私も、駆除技術の開発や技術講座を通じた体制づくりが研究活動と業務にもなっています。
ここで重要なのは、小規模な技術、誰もが手軽に取り組める調査や駆除方法を提示することです。スマホカメラ撮影法や環境DNAによる判定、安全性の高い薬剤や簡便な隙間充填(じゅうてん)剤の開発、廃漁網による防虫などの研究開発を進めています。小さな虫を探し出して対策するには多くの眼と手が必要です。地域との協働や学術知識、駆除技術、制度設計、普及教育を組み合わせて課題解決することが求められます。外来生物対策は博物館との親和性が高い応用研究領域となっています。

-
東播三田北播丹波

-
三田阪神

-
三田

-
三田地方行政

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田地方行政教育

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田選挙地方行政神戸

-
三田選挙

-
文化フェス主義!三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田地方行政

-
三田

-
三田地方行政

-
三田

-
三田スポーツ

-
三田

-
三田

-
三田

-
選挙三田

-
三田

-
丹波三田野球

-
三田連載三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田選挙

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田連載三田

-
三田地方行政選挙

-
三田選挙

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田地方行政

-
但馬丹波三田阪神姫路西播

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田選挙

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田スポーツ

-
三田連載三田

-
三田地方行政

-
三田地方行政

-
三田地方行政

-
三田地方行政

-
三田

-
東播三木三田

-
三田神戸

-
三田連載三田

-
三田

-
三田文化

-
三田地方行政

-
三田

-
三田

-
三田

-
三田地方行政

-
三田

-
三田選挙

-
三田

-
三田

-
三田連載三田

-
三田文化

-
三田地方行政

-
三田

-
三田地方行政阪神

-
三田地方行政

-
三田教育

-
三田連載三田

-
三田

-
三田地方行政

-
三田地方行政

-
三田

-
三田

-
三田地方行政

-
三田地方行政

-
三田地方行政

-
三田神戸

-
三田地方行政

-
三田