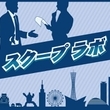30代から認知症の祖母と、脳梗塞の母を介護してきた奥村シンゴさん(42)=兵庫県宝塚市=が、病気や障害がある家族を若くして世話する「ヤングケアラー」「若者ケアラー」の問題に光を当てようと、書籍やインターネットで体験記を執筆している。学業や結婚、就労とライフステージ全般への影響が懸念されるが、顕在化しにくい。「介護作家」を名乗り、支援グループも運営する奥村さんは「社会が変わるきっかけをつくりたい」と語る。(佐藤健介)
IT企業などでキャリアを積んでいた奥村さん。暮らしが一変したのは2012年秋、32歳の時だった。母が脳梗塞を、祖母が認知症を同じ時期に発症した。
弟と妹は結婚して家庭を持っていた。きょうだいで唯一独身で「おばあちゃん子」だった奥村さんが、仕事をやめて祖母の在宅介護を決意。病気がちな母を支え、孫に不自由な暮らしをさせまいと70代まで働いてくれた恩返しでもあった。
祖母は同じ話を繰り返したり、調理前の食材を口に入れたり。収入源がなく貯金は減るばかりで、生活不安もつきまとった。
それでも、交際する女性も30代の頃に両親の介護をしており、悩みを分かち合って心身の疲労を和らげた。祖母の要介護度が上がってデイサービスやショートステイが利用しやすくなると、少し負担が軽減した。
「自らの経験を伝え、介護で悩む人らを救いたい」と考え、15年にフリーライターとして仕事を再開した。ペンネームでデジタルメディアへの寄稿のほか、講演にも励む。
祖母が19年に入院して在宅での介護に区切りをつけると、20年に「おばあちゃんは、ぼくが介護します。」(法研)を出版。テレワークを活用する▽同世代の経験者に愚痴を言う-など思い詰めないための心がけや新型コロナウイルスを含む感染症対策を紹介した。
さらに、若者介護者のコミュニティー「よしてよせての会」を21年9月に設立した。関西弁で「仲間に入れて」の意味で、当事者が楽しめるクリスマス会や恋愛応援イベントなどを企画。ケアラーのエピソードを読み物にしたり、医療・介護の専門家に取材したりして情報を発信。また国に対し、困窮する若者介護者への給付金や、ケアを一時的に代行する「レスパイトサービス」の充実を求める。
祖母の療養に付き添い、がんなどで入退院を繰り返す母も世話するなど、在宅以外でもケアが必要な状況は続く。だからこそ、活動にいっそう使命感を抱く。
「核家族化や少子高齢化が進む中、介護で孤立しがちな子どもの問題を広く認知してほしい。介護離職の防止や再就職の公的支援につながれば」と願う。
奥村さんのメールアドレスはshingo37.01@gmail.com
◇ ◇
■介護離職年9万9000人/神戸市に支援専門部署
家族のケアを担う若者は家事全般に加え、入浴や排せつ介助、薬や金銭の管理も強いられる。「介護は家庭の責任」との認識も根強い中、実態の把握と支援体制の構築は急務だ。
日本ケアラー連盟(東京)は、18歳未満を「ヤングケアラー」、18歳からおおむね30代までを「若者ケアラー」と定義する。総務省によると、家族を介護する15歳~30代は約54万人で、介護による離職者は年間約9万9千人。同連盟はサイトで支援グループの連絡先を掲載している。
国は2021年4月、中学生の約17人に1人が、高校生の約24人に1人が「世話する家族がいる」とする初の調査結果を公表。対象となる若者の調査や福祉機関職員らの研修を行う自治体を助成し、対象世帯の家事・育児を支援する方針だ。
兵庫県では、20代女性が1人で介護していた祖母を殺害する事件が19年に起きた神戸市が、成人を含む「こども・若者ケアラー」を対象とした専門部署を21年6月から置き、当事者の居場所「ふぅのひろば」を開設。兵庫県社会福祉事業団も県内9カ所で運営する高齢者施設に相談窓口を設けている。