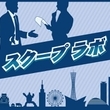わが子に対する「性教育」と言うと、性行為や体の成長について教えるというイメージが強く、つい身構えてしまいがちだ。だが、自分の心と体の大切さを知ってもらうことが、性教育の第一歩。それが自分を守り、他人を大事にする気持ちを育むことにつながる。性教育講座などを展開するNPO法人「HIKIDASHI(ヒキダシ)」代表の大石真那(まな)さん(41)=兵庫県明石市=は「幼児期から家庭で性教育に取り組むメリットはたくさんある。できそうなことから始めてみて」と呼びかける。(小尾絵生)
性教育の始め時は3歳ごろと言われることが多い。子どもが気恥ずかしさを覚えずに、素直に理解してくれる年ごろだからだ。加えて、スマートフォンやタブレットなどが子どもにとって身近になり、さまざまな情報に触れる時期が格段に早まっていることも背景にある。
「何も知らなければ、性に関する誤った情報に無防備にさらされてしまう。性暴力の当事者にならないためにも性教育は重要」。3男1女の母親でもある大石さんはこう強調する。
■「嫌と言っていい」
日本の性教育は、若者の性行動を早めるのではという誤った認識から、世界的に見てかなり遅れているのが現状だ。性交について学校の授業で扱うこともなく、間違った知識が原因で、予期せぬ妊娠に至ることもある。
大石さんは「思春期になってからではハードルが高く、幼いときから家庭で繰り返し伝えていくのがいい」と指摘する。
とはいえ、保護者は何から教えればいいのか。大石さんは「嫌と思った時は嫌だと言っていいということを伝えてみて」とアドバイスする。
胸、性器、尻など水着で隠れる部分に口を加えて「プライベートゾーン」と呼ばれる。それらを含め、自らの体をどう触っていいかは、自分自身に決める権利があることを理解してもらうことが大切だ。
「相手の『嫌』も尊重するという考えが大事。同意に基づいて行動するという意識は、対人関係の基盤になる」と大石さん。
このことは家族の間でも同じだ。愛情表現や世話のために、子どものプライベートゾーンに触れるときには、声をかけるなど同意を得てからにしよう。たまに大石さんも長女から「ママ、忘れてない?」と同意を得てないことを指摘されるそうだ。
■「タブーを作らない」
特に親が戸惑うのは、セックスや子どもができる仕組みを尋ねられた時だろう。「答えにくい」と思った質問には、科学的に淡々と語るのがこつだという。
大石さんが長男に性交の話をした際には「『それ、虫の交尾やな!』と拍子抜けするほどあっさり理解してくれた」と振り返る。すぐに答えられなくても、「いい質問だね。あとで一緒に調べてみようか」などと話し、絵本の力を借りてみるのもいい。
注意したいのは、性の話題をタブーとする雰囲気を作らないこと。何か問題が起きた時にも話せる関係性を築くのも重要だ。
大石さんは「子どもは親の反応にとても敏感。話題にしてはいけないことだったかも、と思わせないよう堂々と答えて」と力を込めた。
■月経教える絵本「げっけいのはなし いのちのはなし」も出版
大石さんは昨年、絵本「げっけいのはなし いのちのはなし」(みらいパブリッシング)を出版した。月経の仕組みや、赤ちゃんが生まれるまでの過程を描く。
大石さんが子どもの性教育に関心を持つきっかけが4人目の子どもに当たる長女(5)の妊娠だという。当時、保健師として兵庫県で働いており、基本的な知識はあったものの、子どもに妊娠の仕組みなどを説明するために勉強し直したのだそうだ。
やがて性教育に関する講座などを開くようになり、月経の仕組みなどを解説する絵本を探したが、これといったものが見つからなかったという。出版社が主催するコンテストに絵本のストーリーを応募すると奨励賞に選ばれ、出版の道が開けた。
作品は小学3年生の「たろう」が、母親の月経による出血を見つけたところから始まる。子宮や卵巣の働き、性交などについて、優しいタッチの絵で分かりやすく表現している。
実際に子どもにどのように性の話をすればいいのか一例となるように心掛け、大石さん自身と息子の実際の会話をせりふに盛り込むなど工夫したという。
「げっけいの-」は1430円。韓国で今年6月、翻訳版が出版され、台湾でも刊行が決まっている。(小尾絵生)