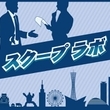認知症への対策を神戸大教授らに聞くこのシリーズ。前回は認知症と、高血圧や糖尿病など生活習慣病との関連や予防法について紹介しました。認知症の予防的取り組みは、40代からの中年期が重要と言いますが、具体的にどうすればよいのでしょうか。医師で神戸大大学院保健学研究科の古和久朋教授(48)に、年代ごとの課題や注意すべきことを聞きました。(聞き手・小西博美)
-認知症の予防研究は世界各国で行われている。
「先日の公開シンポジウムでは『フィンガー研究』が話題になりました。フィンランドの住民を対象に認知機能低下の予防を目的に行った研究で、病気や運動、栄養、生活習慣などの指導をした結果、全く生活に介入しなかった人に比べて認知機能が改善する傾向が見られたとの結果でした。オランダやフランスでも同様の研究が進んでいます」
-なぜそういう流れに。
「日々患者さんを診ていると、やはりこの病気は薬の開発より先に、少しでも早く発症前に気付かないと患者を減らすことにつながらないと感じます。最近の治験では、認知症の症状はないが、脳にその原因となる老人斑がたまった人を対象にしています。症状が出るのを待っているのでは遅すぎます。適度な運動を行い、生活習慣病を改善してそれでも兆候が出たら治験をすればよい。いずれ、日本でもそういう研究をすることになるでしょう」
-認知症予防はいつから始めれば?
「早ければ早いほどいいでしょう。20、30代は脳をつくる時期。勉強して頭を使い、仕事も複雑な決定やいろいろなことを考える作業をする方がよいと言われます。30歳まで脳は成長します。脳を使うことで情報の受け渡しをする『シナプス』と神経回路を増やし、脳の可塑性を高めることが大切です。それによって認知的な予備力である『コグニティブ・リザーブ』が増えます。すると将来細胞の数が減っても残る機能が多くなる。富士山を5合目から下りるのと、頂上から下りるのとどちらが早く地上に着くかということです」
「また、フィンランドの限定的な地域と年代の人が対象ですが、9、10歳の成績が低い人はそうでない人より、将来の認知症リスクが高いとの研究結果も報告されています」
-ポイントは中年期。
「40代からそのリスクを知り、高血圧や糖尿病を治療し、コレステロール値を下げることが重要です。それらを放置すれば万病のもとになりがんや心筋梗塞、脳梗塞に直結するだけでなく、認知症にもつながることがデータで出ています。さらに、飲酒は適量にとどめ禁煙する。ストレスをためないなど精神的な健康を保つことも大事です」
-そして高齢期には。
「60~80代になると、加齢に伴って筋力が衰え、気力も落ちる『フレイル』や、コミュニケーションが問題になってきます。外にどれだけ出掛けているか、役割があるかによって、コミュニケーションの質量も変わります。うつもリスク因子なので、対応する必要があるでしょう」
-他国の認知症の現状は。
「英国では、国がパンに入れる塩分量の上限を下げ、その結果発症率が下がっていると考えられます。米国も低下傾向にあり、大卒が増えたからではと推測されています。一方、日本では大学へ行き始めた団塊の世代が今後75歳以上になります。それ以前の人たちは戦争などで教育歴の低い人が多かった。大卒が増えることで発症の低下が期待される半面、高齢者数自体が多く思うように減らないかもしれません」
【こわ・ひさとも】1970年、東京都生まれ。95年東京大医学部卒。2004年3月、同大大学院修了。同大学病院で認知症専門外来を立ち上げ、10年に神戸大へ。認知症専門医として診療に携わる一方、認知症予防の講演も行う。17年から現職。芦屋市在住。