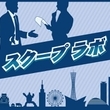「あれっ、おかしいな。こんなに多いのか?」
昨年十一月、神戸大医学部の地下一階。パソコンで膨大な検視記録を検索していた長崎靖・兵庫県監察医は、思わず画面を見つめ直した。
自宅で誰にもみとられずに亡くなる「独居死」。担当する神戸市内(北、西区を除く)で、前年の総数は三百六十一人だった。約十年前の一・五倍。
阪神・淡路大震災の仮設住宅や復興住宅であぶり出された問題が、一般住宅にも広がっていた。
「頭では分かっていた。しかし、数字にして突き付けられると、驚かざるを得ない」。日常的に死に接する監察医自身、予想を超えた数字だった。
ならば、被災地外でも同じ状況なのか。全国ではどうか。兵庫県や省庁に尋ねた。
「そんなデータの取り方はしていない」
あれほどクローズアップされた独居死は、今や実態さえ把握されていない。
◆
各警察署や関心のある法医学者らに協力を求め、現状の一端が見えた。
二〇〇二年、兵庫県で七百七十人以上。自殺を除いたデータは大阪府で千六十人(〇一年、七十歳以上)、徳島県では百一人(〇二年、六十五歳以上)。いずれも総数は急増、発見までの期間は長期化していた。
上野易弘・神戸大教授(法医学)は、高齢化や核家族化に伴う独居高齢者の増加が背景にあるという。さらに、地域のつながりの希薄化を要因に挙げた。
こうした「指摘」は、阪神・淡路後、何度も繰り返された。
震災では要救助者約三万五千人の八割が、隣人らに救出された。とりわけ津名郡北淡町では、住民が互いのことを熟知し、生き埋めになった人を速やかに救助できたとされる。
一九九六年、全面改訂された兵庫県の地域防災計画もこう明記する。「平時の住民相互の助け合いや適切なケアサービスの供給が、災害弱者対策にもつながる」
だとすれば、独居死が日常化する社会は、どうなるのか。
◆
生活援助員、見守り推進員、民生委員…。神戸市は独居高齢者らの見守り対策に、約二千六百人の人材と千三百のグループ、年間七億七千万円(〇三年度)の予算をつぎ込む。
しかし「行き過ぎれば、監視につながりかねない。見守りは基本的に自己申告」と同市高齢福祉課。
地域主体の模索も続く。同市長田区の御蔵通五・六・七丁目自治会は、高齢世帯の状況を詳しく示す「コミュニティーマップ」を作り始めた。地域を二十に分け、役員らで見守る計画だ。
浦野正樹・早稲田大教授(災害社会学)が言う。「会社に行っているときに地震が起こり、親や子どもが家に取り残される可能性もある。誰もが災害弱者になり得る。自分や家族の身を守るには、地域を守らなければならない」