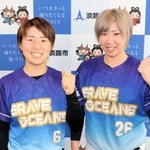伊弉諾神宮(兵庫県淡路市多賀)由来の原材料にこだわった日本酒を、吉備国際大学農学部醸造学科(南あわじ市志知佐礼尾)の学生たちが完成させた。難題だった酵母の採取に3年を費やした。学生たちは今月初め、同神宮の神職による「呑み切り神事」で出来栄えを確認し「言葉にならない感動的な味」と感慨に浸った。
(内田世紀)
伊弉諾神宮の酒を造るプロジェクトは2020年度、同学科・井上守正教授の研究室で始まった。同神宮のブランド力を生かした新商品を開発し、地域の活性化に役立てようと発案。当時2年生の3人が参加した。原料の米は同神宮の「御齋田(ごさいでん)」で栽培したイセヒカリを使うことに決めたが、酵母が課題になった。
日本酒造りは、蒸した米をこうじ菌で発酵させでんぷんから糖を生成。その糖を酵母で発酵させてアルコールを醸造する。酵母が酒の味や香りを大きく左右するといい、多くの酒蔵が日本醸造協会(東京都)が提供する「きょうかい酵母」を使っている。
酵母は空気中や木、石の表面など、自然界のどこにでも存在する。学生たちは神宮の境内で酵母を採取することにした。
1年目、神木や社殿などに培養液を含ませた和紙を貼り、酵母が付着するのを待った。しかし、日本酒造りに適した酵母は見つからなかった。
2年目からは、当時3年の因來(いなき)理紗さんと同2年の島本巧さんが参加。神宮の協力を得て通常は入れない本殿付近で採取したが、進展はなかった。
3年目の昨年度も、因來さんと島本さんは諦めずに挑戦。和紙の培地が乾燥しないようにするなど工夫を凝らし、100個以上のサンプルを採取した。2人は「酵母がいると信じていた」と振り返る。
そして昨年8月、本殿に上がる階段の下で、石に貼った培地に酵母らしきものが付着した。研究室で培養し遺伝子解析などを経て、日本酒の醸造に適した酵母であることが確認された。4種の株を作り、その中から本名孝至宮司が「香りが最も良い」という1株を選んだ。
□
酒の仕込みは、同神宮の神酒を造っている「千年一酒造」(同市久留麻)が引き受けた。未知の酵母が同社の酵母に悪影響を与えないよう、全ての酒の仕込みを終えた3月末に始めた。
仕込みには現3年の木上晴登さんが加わり、洗米やもろみ造りなどに取り組んだ。発酵は順調に進み、4月26日にもろみを搾って酒が完成した。
5月1日、本名宮司らが酒蔵を訪れ、完成した酒を初めて味わう「呑み切り神事」を行った。同大関係者ら約20人が参列。伝統的な装束「白丁」に身を包んだ学生3人がタンクの栓を開けて杯に注ぎ、一同は乾杯で完成を祝った。
「酵母が見つかった石は、そこにあった陵を形成していたと考えられる『聖石』。古い時代の良いお酒を再現できたのではないか」と本名宮司。新たな酒の名として「神陵(みささぎ)」「那岐(なぎ)の陵(おか)」「神宅(かむやけ)の杜(もり)」の候補を挙げた。
同社の上野山善彦杜氏(とうじ)は「酵母の性質が分からない中での酒造りだったが、辛口のすっきりした酒ができた。諦めずに頑張った学生をたたえたい」と話し、商品化も視野に入れる。
島本さんは実家が京都府の酒造会社だといい「貴重な経験ができた。将来は人生を豊かにするような酒を造っていきたい」と満足そうに話した。今春卒業した因來さんは「今までに飲んだことのない味と香り。完成は言葉にできないほどうれしい」と喜んだ。

-
淡路

-
淡路地方行政

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路野球

-
淡路野球

-
神戸淡路

-
淡路

-
淡路#インスタ

-
淡路

-
淡路

-
スポーツ野球淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路野球

-
淡路#インスタ

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路選挙

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路地方行政

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
神戸阪神明石淡路

-
淡路阪神神戸東播姫路

-
淡路

-
淡路阪神明石神戸

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路スポーツ

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
地方行政淡路

-
淡路

-
淡路地方行政

-
淡路

-
淡路

-
淡路#インスタ

-
淡路

-
淡路文化

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路神戸高校スポーツ陸上

-
淡路神戸

-
淡路文化

-
淡路スポーツ

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路地方行政

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路#インスタ

-
淡路

-
淡路

-
淡路未来を変える

-
淡路

-
淡路

-
淡路

-
淡路#インスタ

-
淡路

-
淡路

-
淡路スポーツ

-
阪神淡路但馬