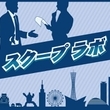認知症の対策について神戸大教授らに聞くこのシリーズ。前回は認知症予防に効果があるとされる食品について紹介しました。認知症予防では、健康な状態から要介護に移る中間段階「フレイル」に陥らないための対策も、効果があるとされます。自分自身がフレイル状態にあるかどうかのチェック方法や予防に役立つ食事について、内科医でもある神戸大大学院保健学研究科の安田尚史教授(54)に聞きました。(聞き手・貝原加奈)
-なぜ今フレイルが注目されているのでしょうか。
「フレイルとは、筋力の低下や疲れなど、加齢に伴い生じる機能低下全般のことで、要介護状態の前段階を指します。フレイルには、筋力が低下する『サルコペニア』などの身体的要素▽認知症やうつなどの精神的要素▽1人暮らしなど社会的要素-の三つがあります。一つでも当てはまると、『フレイルサイクル』という悪循環に陥ります。例えば、低栄養で筋肉量が減ると、家にこもりがちになり、気分が落ち込みやすくなります」
-どんな人がなりやすいのですか。
「高血圧や糖尿病などの生活習慣病、あるいは認知機能障害やサルコペニアなど老年症候群の人は、特に注意が必要です。高齢期ではメタボリック症候群対策でカロリー摂取を過度に控えると、フレイルを助長する場合も。ただ、早く気付いて適切な対策をすれば、健常な状態に戻るので、国も高齢者の介護予防対策の柱に据えています」
-自分でチェックはできますか。
「評価する指標として、偏食などによる低栄養▽移動歩行速度の低下(10秒で8~10メートルが目安)▽握力低下▽疲れが取れない▽外出がおっくうになった-の五つがあります=図参照。三つ以上当てはまればフレイル、一つか二つなら一歩手前の『プレフレイル』です。75歳以上の高齢者のうち20~30%はフレイルの段階との報告もあります」
-普段の生活で心掛けたいことは。
「筋肉量は20~30代をピークに減少していきます。中年期に筋力を保つことが大切。適度な運動は大前提ですが、食事面で最も気を付けたいのは、タンパク質の摂取量を維持することです。年を取ると肉や魚の摂取量が減りがちになり、筋力低下につながります。国も摂取量の目標値を上げる案を出すなど、重要性を呼び掛けています」
-どんな食品から取ればよいでしょう。
「肉や魚、乳製品、大豆製品をバランスよく食べてください。ただ、腎臓病や糖尿病の人は動物性のタンパク質が増えると病気に悪影響が出ることがあります。かかりつけ医からの指示に従って大豆製品などを多めに取ってください。1日に体重1キロ当たり1グラムのタンパク質が目安です」
-その他、予防に効果的な食品を教えてください。
「骨を丈夫に保つのに必要なカルシウムを多く含むイワシやシラス、乳製品などです。骨粗しょう症を防ぎ、骨折予防につながります。1日700~800ミリグラムの摂取が理想と言われていますが、意識しないと難しいです。女性は特に、閉経後のホルモン変化により骨粗しょう症が進んでしまうので、より積極的に取りましょう」
「カルシウムの体内への吸収を高めるビタミンDも必須。キノコ類や魚介類に多く含まれます。皮膚で合成されるため、一定程度日光に当たってください。筋肉や骨など、脂肪以外の『除脂肪体重』を保つことを目指しましょう」
【フレイル】老化に伴って身体や認知の機能などが低下し、要介護状態に至る前の段階。「虚弱」という意味の英語「frailty(フレイルティ)」に由来する。適切なケアを行えば健常な状態に戻れるとされる。フレイルのさらに一歩手前の状態をプレフレイルという。
【やすだ・ひさふみ】1964年、姫路市生まれ。神戸大大学院医学研究科修了。同大病院で総合内科専門医、糖尿病専門医として生活習慣病患者らの診療に携わる。同大大学院医学研究科の特命講師を経て、2012年から現職。16年から副研究科長。神戸市在住。