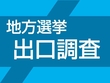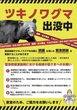7月23日、日米間の関税交渉が大きな節目を迎えた。アメリカのトランプ大統領は、自身のソーシャルメディア「Truth Social」で日本との「大規模な合意」を発表し、日本側も石破茂首相が合意を正式に認めた。
この交渉は、トランプ政権が掲げる「相互関税」政策と自動車関税の引き下げを巡る激しい議論の末に妥結したもので、日本経済と国際貿易に大きな影響を及ぼす内容となっている。しかし、日本が大幅な譲歩を強いられた一方で、今後は対中貿易規制を巡る新たな圧力が予想され、交渉の余波は続く可能性が高い。
■交渉の概要と合意内容
今回の合意では、米国が当初通告していた日本からの輸入品に対する25%の関税を15%に引き下げることが決定された。また、自動車および自動車部品に対する追加関税も半減され、既存の2.5%の税率と合わせて15%に設定された。これは日本が強く求めていた自動車関税の軽減が部分的に実現した形だ。日本側は当初、追加関税の完全撤廃を目指していたが、米国との交渉の難航を経て、関税率の引き下げに方針を転換した。
日本は米国に対して総額5500億ドル(約80兆円)に上る巨額の投資を約束し、その9割が米国の利益に資する内容とされている。さらに、農産物市場の開放として、コメの輸入を75%増加させること、自動車やトラック市場の開放、ボーイング製航空機100機の購入などが合意に含まれた。これにより、米国産農産物の日本市場へのアクセスが拡大し、特にコメについてはミニマムアクセス枠の維持を前提に輸入量が増加する見通しだ。ただし、鉄鋼・アルミニウムに対する50%の追加関税は維持され、防衛や為替に関する合意は含まれなかった。
■日本側の反応と評価
石破首相は記者会見で、対米貿易黒字を抱える国の中で最も低い関税率を実現したと成果を強調し、自動車関税の数量制限なしでの引き下げを「世界に先駆けた成果」とアピールした。自民党内でも、日本の基幹産業と国益を守る重要な成果と評価し、農業や為替、防衛費での一方的な譲歩が回避された点を高く評価した。しかし、国内外の識者や市場関係者の間では、今回の合意が日本にとってどれほどの利益をもたらすかについて意見が分かれている。
一部の専門家は、自動車関税の15%への引き下げは当初の25%から大幅な改善との声が聞こえる一方、5500億ドルの対米投資や農産物市場の開放は、中長期的に国内企業の投資の米国シフトや産業空洞化の懸念を招くとの声もある。
■交渉の背景と日本の戦略
今回の交渉は、トランプ大統領が2025年3月から4月にかけ、自動車や鉄鋼・アルミニウムへの追加関税や一律10%の相互関税を打ち出したことを契機に始まった。日本側は赤澤経済再生担当大臣を交渉の責任者に任命し、3カ月間で7回にわたり米国を訪問するなど、異例の頻度で協議を重ねた。特に自動車関税の引き下げは、日本経済の基幹産業である自動車産業への影響を最小限に抑えるための最優先課題だった。
当初、日本は関税の完全撤廃を主張したが、米国側の強硬な姿勢により目標を下方修正。最終的に、トランプ大統領との70分にわたる直接会談で、1%ごとの関税引き下げに見返りを要求する厳しい交渉を乗り越え、15%での合意に至った。この過程で、日本は「関税より投資」を軸に米国との互恵的な関係を模索し、経済安全保障や貿易拡大の分野でも協力を深める姿勢を示した。
■ 今後の課題は対中貿易規制への圧力
合意に至ったとはいえ、トランプ政権の通商政策は今後も日本に新たな試練を課す可能性が高い。1つに、対中貿易規制を巡る圧力が強まるシナリオが懸念される。トランプ大統領は中国に対する強硬姿勢を鮮明にしており、日本が対中貿易でどのような立場を取るかを注視している。
米国が日本に対して、中国への輸出管理や技術移転の制限を求める可能性は高く、これが日米関係や日本企業のグローバル戦略に新たな緊張をもたらすだろう。
また、今回の合意には共同の合意文書が存在せず、適用時期や投資枠組みの詳細に日米間で認識のずれが生じているとの指摘もある。日本政府は来週にも合意内容の共通認識をまとめた文書を作成する意向だが、トランプ政権の予測不可能性を考慮すると、交渉の不透明感は完全には解消されない。
日米関税交渉の合意は、日本にとって最悪のシナリオを回避した一方で、巨額の対米投資や市場開放という形で大きな譲歩を強いられた。自動車関税の引き下げは一定の成果と言えるが、経済への影響や中長期的な産業構造の変化は注視が必要だ。さらに、トランプ政権の対中政策が日本に新たな圧力を加える可能性があり、引き続き戦略的な対応が求められる。日本は、経済安全保障と国際協力をバランスさせながら、持続可能な通商政策を模索する必要があるだろう。
◆和田大樹(わだ・だいじゅ)外交・安全保障研究者 株式会社 Strategic Intelligence 代表取締役 CEO、一般社団法人日本カウンターインテリジェンス協会理事、清和大学講師などを兼務。研究分野としては、国際政治学、安全保障論、国際テロリズム論、経済安全保障など。大学研究者である一方、実務家として海外に進出する企業向けに地政学・経済安全保障リスクのコンサルティング業務(情報提供、助言、セミナーなど)を行っている。