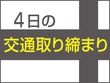発生から5カ月が過ぎた能登半島地震の被災地では、もともとの高齢化と人口減少に今回の被災が重なり、存続が危ぶまれる小規模集落がある。石川県はそうした集落の維持に向け、地元に住み続けられる「石川モデル」を構築した。避難先から地元の集落に造られた仮設住宅へと、仮設住宅間の住み替えを認める仕組みで、県内で唯一、穴水町の下唐川地区でモデル住宅の建設が進んでいる。
■仮設利用後は町営住宅に
下唐川地区は、山の南に東西に延びる集落。穴水町によると、地区内約30世帯のうち、14世帯が全壊、11世帯が大規模半壊と、甚大な被害を受けた。集落が孤立したため、住民らは食料を持ち寄って命をつなぎ、自力で道路を復旧させたという。
自宅の再建を考えているのは数軒だけ。集落にある土地の多くは、土砂災害の危険がある区域に入っているため、家屋再建のハードルは高い。このままでは被害の少なかった家も含め、集落には数世帯しか残らないという。
村にはプレハブ型仮設住宅11戸ができたが、原則2年で退去しなくてはならない。そのため、その後も集落に住み続けたいという住民向けに「ふるさと回帰型応急仮設住宅」、いわゆる石川モデルとして、木造平屋の2DK約30平方メートルの住宅6戸の建設が決まった。