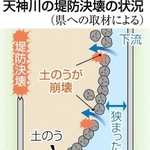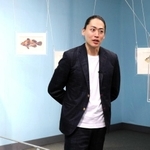兵庫県西宮市の甲山(かぶとやま)中腹にある古刹・神呪寺(かんのうじ)(同市甲山町)で18日、国指定重要文化財で秘仏の「如意輪観音像」が年に1度だけ公開される「融通(ゆうずう)観音大祭」があった。寺はその名称から怖いイメージを持つ人も多いけれど、今年で創建から1190年になるという由緒正しいお寺だ。戦国時代には織田信長の焼き打ちにも遭っている。それなのに秘仏が焼失せず、今も無事なのはなぜかしら?(浮田志保)
神呪寺は平安前期の831年に弘法大師と弟子の如意尼が開き、本尊の如意輪観音像は如意尼がモデルと伝わる。日本三如意輪の一つで、本堂の安置室に鎮座し、1950年から毎年5月18日にだけ公開している。
普段は閉じた扉が開かれ、近づくと、腕が6本。色あせて表情は分かりにくいが、首を傾けて物思いにふけるような姿は、なんだか心を落ち着かせてくれる。
「別名、『融通観音』。戦後から『金を融通してくれる』と言われて商業者の信仰もあついんです」と森田瑛淳住職が話す。
一方で、神呪には「『仏様をたたえる言葉』という意味があり、『神を呪(のろ)う』ではないですよ」とも。そして、観音像を巡る物語を教えてくれた。
◇
寺から南東に3・5キロ。阪急電鉄今津線の門戸厄神駅付近に「神呪町」という地名がある。
戦国末期、寺は有岡城(現伊丹市)城主の荒木村重を支援したとして織田信長に焼き打ちにされ、豊臣秀吉の太閤(たいこう)検地で寺領を半分に減らされると、僧たちは甲山を降りて暮らし始めた。それで寺の名前をとったのが神呪町の由縁という。
寺が“里帰り”できたのは、それから約170年後のこと。徳川5代将軍綱吉の母・桂昌院(けいしょういん)が200両を差し出すなどして神呪町付近に一時復元された後、江戸中期の1749年、ようやく今の場所に再建された。
その間、僧たちは転々としつつも観音像を大切に守ってきたというわけだ。
◇
でも、ちょっと待って。肝心の焼き打ちで焼失しなかったのはなぜなの?
すると、森田住職は淡々と「実はね、本堂の裏に井戸があるんです」。
焼き打ち直前、僧たちが観音像をその井戸に隠して守ったという伝承が受け継がれているという。残念ながら井戸は公開禁止で見せてもらえなかったが、こんな話を聞かせてくれた。
「融通観音と言うでしょう。でも、本当の融通は『互いを思いやる心』です。相手を気遣う大切さを思い出してもらえたら」
確かに、絶体絶命の危機に直面しても、流浪(るろう)の身になっても人々に守られてきた観音像には、思いやりの心が具現化されているのかもしれない。
大祭では例年通り、僧たちが本堂で読経をした。創建1190年の節目も目立った行事はしないという。
「コロナ禍で人々の交流が難しくても、相手の身になって考える社会であってほしい」と森田住職。温かい心に触れた気がして、山を下りた。

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
三田阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化神戸阪神

-
阪神地方行政

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
スポーツ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神スポーツストークス

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神明石神戸

-
阪神地方行政

-
おくやみ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
新型コロナ姫路阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神タカラヅカ

-
阪神

-
阪神スポーツバレー

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
教育阪神

-
阪神

-
阪神#インスタ

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神バスケ

-
阪神

-
阪神選挙

-
阪神岡崎慎司×兵庫

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神連載阪神

-
阪神

-
選挙神戸阪神

-
阪神

-
LGBT阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
神戸阪神明石淡路

-
淡路阪神神戸東播姫路

-
阪神

-
阪神