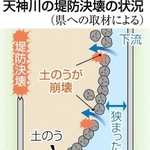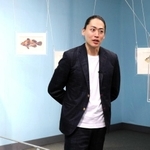地域でそれぞれ確かな存在感を示しながら、今は姿を消した「旧名所」があります。
古くから都市部として発展し、多くの人や物を集めてきた阪神地域はその宝庫です。人気だった娯楽施設や、生活の中のランドマークに加え、先の戦争の記憶も…。
その面影と時代の空気を探して歩きました。(2020年8月の連載から=肩書、年齢は当時)
■尼崎・大物川 ごみの川“緑の回廊”に 公害、埋め立て、今は市民の癒やし
阪神電鉄大物駅(尼崎市大物町)を東側に出ると、樹木が生い茂る緑地帯が、線路の高架をくぐって南北に伸びている。南は幅約15~50メートルの緑道が蛇行しながら断続的に約1キロ続き、北側も曲がりくねった道路沿いに公園が広がる。
この“緑の回廊”は昭和半ばまで「大物川」という川だった。どす黒くよどむごみの川-。工都・尼崎の暗部を象徴し、その克服の“犠牲”となって地中に消えた。
大物は、源義経と弁慶が頼朝の追討を逃れるため船出したと伝わる歴史的な場所。明治中期の地図を見ると、細い支流が田畑を潤しながら南下し、今の国道2号の北側で合流する。そこからが大物川となり、さらに蛇行しながら南に流れ、海に向かっていた。
「昔は泳げたし、水浴びもできた-と戦後間もない頃に聞いた」と話すのは、尼崎市で長く公園行政などを担った榎本利明さん(92)。淡水と海水が混じった汽水域だったのか、シジミが多く取れたという。大物駅の南には「蜆橋(しじみはし)」という名の橋もあった。
しかし尼崎が工業都市として発展するにつれ、大物川周辺には多くの工場が立地した。荷を運ぶ船の往来で活況を呈する一方、排水が流れ込んだ。1934(昭和9)年生まれで、川の近くで育った羽間美智子さん(86)は「川の水は黒かった。泳いで遊んだ記憶はないですね」と振り返る。
川はさらに汚れていく。
尼崎の臨海部などでは、大正期から戦後にかけて、工場が地下水をくみ上げた影響で地盤沈下が進み、川の水が流れなくなった。大物川も自らの浄化能力を失うことになる。昭和30年代には、家庭ごみなどがたまりにたまり、ごみ捨て場同然になっていたという。
川底を掘って流れをよみがえらせる方法もあった。だが、かつて水を供給した田畑は住宅や工場に変わり、水運もトラックにその座を譲っていた。
「浚渫(しゅんせつ)してまで残す価値はなかった」と榎本さん。大物川は65(同40)年から5年で埋められた。
跡地の活用で議論があった。市では当初、住宅地などとして売り、固定資産税を得る方針が有力だったという。榎本さんは抵抗した。公害が深刻化していた。市民の要望もあり、「このまちには緑が必要」と、まだ少なかった緑地の造成を訴えた。
利点を理論的に説明する文書を大学教授に作ってもらい、庁内や市議会を説得。「公害のまちを何とかせないかん、という考えはみんな持っていた」。主張は受け入れられた。
多くの木々を植えた。「歴史と憩いの散歩道」として、橋の跡などを示す碑も各所に建てられ、春には満開の桜を見ながら散策できる緑道になった。細い支流は遊歩道に。川をまたぐ国道2号の稲川橋をくぐるように地下道を通し、住民が安全に国道を横断できるよう利便性も高めた。
大物川の埋め立てとほぼ同時期から、市は「緑を育てる尼崎」を掲げて緑化事業を進め、市内の公園は当時の3倍以上となる345カ所に増えた。その一翼を担った緑の道は、市民を安らぎへと導く。公害の記憶を地中に秘め、木陰を行く人々の日々を癒やしている。

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
三田阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化神戸阪神

-
阪神地方行政

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
スポーツ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神スポーツストークス

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神明石神戸

-
阪神地方行政

-
おくやみ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
新型コロナ姫路阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神タカラヅカ

-
阪神

-
阪神スポーツバレー

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
教育阪神

-
阪神

-
阪神#インスタ

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神バスケ

-
阪神

-
阪神選挙

-
阪神岡崎慎司×兵庫

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神連載阪神

-
阪神

-
選挙神戸阪神

-
阪神

-
LGBT阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
神戸阪神明石淡路

-
淡路阪神神戸東播姫路

-
阪神

-
阪神