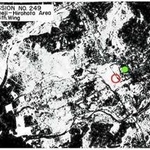なぜ、姫路城の「空襲回避説」は広がったのか。
その遠因の一つとみられるのが、米国人美術家ラングドン・ウォーナー(1881~1955年)が戦前、日本の重要な文化財として米政府に提出した「ウォーナー・リスト」だ。
同リストは全国の151施設をリストアップ。この中に、法隆寺、二条城、伊勢神宮などとともに姫路城が含まれていた。
空襲では100以上の都市が対象になり、七つの城の天守閣が焼失。ところが、京都や奈良の被害は軽微だったため、戦後、同リストなどを根拠に「米軍は文化遺産の価値を理解し、攻撃しなかった」という説が広がった。
1980年以降は、開示された米軍資料の研究が進み、同リストは「米軍の判断とは無関係で文化財保護に特段の関心はなかった」との見方が定着している。
こんな指摘もある。7月3日の姫路大空襲の「戦術作戦任務報告書」を翻訳した郷土研究家、辻川敦さん=尼崎市=は「米軍の作戦計画に姫路城を攻撃しろという文言はない」としながら、空襲をする際の「攻撃中心点」の近さに注目した。
「無差別爆撃が市街地を面として焼き払うことを目的にした以上、姫路城を守る意図があったとは考えられない。残ったのは全くの偶然だろう」と指摘する。
実際、三の丸にあった鷺城中学は焼夷弾で焼失し、大天守にも「不発弾があった」とする手記を、処理に当たった元士官が残している。
95年当時、姫路大空襲に加わったB29の機長アーサー・トームズさんを取材した播磨学研究所の中元孝迪所長は「100機以上が攻撃参加した空襲で、他のパイロットもトームズさんと同じ判断をしたと推測するのは難しい」と慎重な姿勢を示す。
だが「市街地に比べ、城が集中的に攻撃を受けていないことは確かで、レーダーが堀に反応したという『偶然の中の必然』によって、城は守られたと言えるのではないか」と話す。