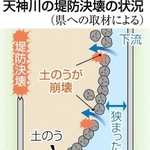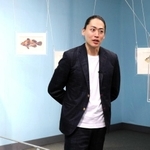■情報いち早く。生放送こそ命
生放送こそ命。そう考えるラジオ人がいる。「いち早く、地域のことを」。緊急時にリアルタイムで情報を差し込める。そこにコミュニティーFMの存在価値がある。「エフエムあまがさき」の楠見正之(64)は、組織内の異動でたまたま局運営に関わるようになった。それでも、阪神・淡路大震災のときの経験があるからこそ、ラジオの使命をかみしめる。
◇ ◇
26年前は財団法人尼崎市総合文化センター(現・兵庫県尼崎市文化振興財団)の施設担当職員だった。1月17日は休館日。北陸へスキーに出掛け、道中のコンビニで聞いたラジオで阪神・淡路大震災が起きたことを知った。伊丹市の自宅に電話を掛けると、妻の悲鳴のような声が聞こえた。
慌てて車で家へ帰る間、ラジオから情報が飛び込んでくる。「高速道路が倒れた」「自衛隊のヘリコプターが状況を確認中」-。5時間後、帰宅すると、電気もガスも水も止まっていた。だが一番驚いたのは、家にいた妻が何も知らなかったこと。家にはラジオがなく、身の回りのこと以外、震災の何一つも伝わっていなかった。
遠く離れた自分はラジオから情報を得られたのに。「ラジオってすごいな」
◇ ◇
尼崎市がコミュニティーFM局の開設を検討し始めたのは震災から5カ月後。市民から「地元の情報が少ない。届かない」と苦情が寄せられていた。
たとえライフラインが途絶えても、情報を伝える手段が必要-。市などの出資で1996年8月、株式会社「エフエムあまがさき」が設立され、同10月に放送が始まった。ただ経営は厳しく、2009年4月、局の経営は財団法人尼崎市総合文化センターに譲渡される。
楠見は財団職員として、ラジオと無縁の仕事をしてきた。それが局の経営譲渡と同時に異動。運営を担当することになる。
スマホの時代。18年の台風21号で市内が停電した時、若いスタッフが「スマホが充電できなくてへこむ」と話すのを聞いてはっとした。「南海トラフ地震がいつ起きるか。電話も電気も使えなくても、放送局さえ残っていたらラジオから情報が得られる」
そのときのために-。リアルタイムにこだわり、朝も昼も夕方も、生放送を続ける。
◇ ◇
震災当時は東消防署の消防係長、尼崎JR脱線事故では中消防署長、東日本大震災の時は尼崎市消防局長として、大きな災害に向き合ってきた。
そこで得た教訓を、野草信次(68)は防災キャスターとして市民に伝える。各地で起きた災害の原因や被害状況を分析し、教訓を伝える毎週土曜の番組「防災一口メモ」を担当する。
やはり重視するのは、情報を伝えるということ。防災への備えで一番怖いのは、慣れや正常性バイアスだと知っている。「『大丈夫だろう。そんなに大したことないだろう』と思っていないか」。気にしすぎなくていい。でも日常の中で、時々思い出してほしい。そんな思いで放送に臨む。=敬称略=
(中川 恵)
【エフエムあまがさき】ステーションネームはFMaiai(エフエムアイアイ)。阪神・淡路大震災で地域情報の伝達手段としてコミュニティーFMの重要性が指摘され、尼崎市などが1996年、株式会社エフエムあまがさきを設立。2009年に尼崎市総合文化センターが放送事業を継承した。周波数は82・0メガヘルツ。同センターにあるスタジオから放送し、聴取エリアは尼崎市一帯や伊丹市、大阪府豊中市など。

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
三田阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化神戸阪神

-
阪神地方行政

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
スポーツ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神スポーツストークス

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神明石神戸

-
阪神地方行政

-
おくやみ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
新型コロナ姫路阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神タカラヅカ

-
阪神

-
阪神スポーツバレー

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
教育阪神

-
阪神

-
阪神#インスタ

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神バスケ

-
阪神

-
阪神選挙

-
阪神岡崎慎司×兵庫

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神連載阪神

-
阪神

-
選挙神戸阪神

-
阪神

-
LGBT阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
神戸阪神明石淡路

-
淡路阪神神戸東播姫路

-
阪神

-
阪神