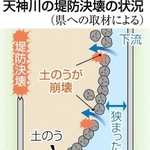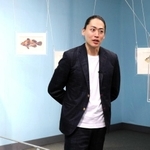尼崎、略して「アマ」。普段何げなく呼んでいるこの呼び名、地元住民だけでなく、全国的にも認知されている。時に上品さとは真逆であるという皮肉を込めた言い方で、ある時には街への親しみを込めた愛称として。市内外の人たちが「アマ、アマ」と呼び習わす。いつから「アマ」なのか、なぜ「アマ」なのか-。(村上貴浩)
「尼崎」は元々、現在の阪神大物駅より南の臨海部を指す地名だった。漁師や海に関わる仕事に就く人々を表す「尼」という言葉と、海に突き出た土地を表す「崎」が組み合わさってできた地名だという。
兵庫県尼崎市立博物館地域研究資料室の辻川敦さん(60)は「江戸時代は武士の街。全ての武士が没落し、職人や工場労働者として工業の町を発展させた。気の強い昔かたぎの人が多い地域」と説明する。
戦後、近代化が進み、急速に工場が乱立したことで工業の街として大きく発展したが、公害問題や治安の悪さといった悪いイメージも目立つようになった。
そのイメージは徐々に定着し、事件や事故などのたびに「これやからアマは-」などと、ネガティブな呼び名として「アマ」が使われることが増えていった。尼崎出身のお笑いタレントが面白おかしく「アマ、アマ」と言うのも、そのイメージを助長しているとの指摘もある。
しかし「アマ」の名の下、一概に悪いイメージばかり強調されることに異論を唱える人もいる。幼少期から長年、尼崎市に住んでいる50代男性は「尼崎は個性的な街。地域の人たちは時に自虐的に略称を使う時もあるが、それは自分たちの街に誇りを持っているから。街の個性が詰まった愛称です」と胸を張った。
◆
「アマ」という呼び名の歴史をさかのぼると、江戸時代後期には既に存在していたことがわかっている。大阪出身の喜田川守貞という人物が江戸時代の生活や風俗を記した「守貞漫稿(もりさだまんこう)」の一部分には「摂の尼ヶ崎略て尼とのみも云(原文ママ)」と書かれ、「尼」と漢字1文字に略されていたことがわかる。
また、尼崎市の伝統野菜「尼イモ」からは、略称が誰によって使われ始めたかが推測できる。「尼イモ」は尼崎で育てられたサツマイモの一種で、戦前に大阪や京都の料亭で重宝されていた歴史がある。特に尼崎の地域だけに存在する特別な品種だったわけではないので、地元の人々にとってはただのサツマイモでしかなかった。
しかし、1891(明治24)年の資料「兵庫県著名農産物栽培録」には「アマイモ」と明記されている。尼崎の名産品として他の産地と区別するため、大阪や京都などの食通たちが呼び始めたと考えられる。
◆
近年、尼崎市は工場跡地の再開発などによって、家族連れや若い世代の住人が増えた。2018年には民間企業の調査で、JR尼崎駅前が「本当に住みやすい街大賞in関西」で1位に輝いた。時代とともに「アマ」が皮肉交じりに使われることは減り、親しみを込めた愛称として使われる機会が増えている。
地元の尼崎信用金庫は「あましん」と呼ばれ、尼崎市には「あまっこ」と名付けられた女の子のマスコットキャラクターがいる。商業施設でも「尼崎」と「ごった返す」という意味を組み合わせた阪神尼崎駅前の「アマゴッタ」が、地元住民らに親しまれている。
時代とともに意味が変化する略称「アマ」。今や、そこに込められる思いは、街への親しみしかない。
◇ ◇
■国語学専門、元大学教授の考察は…
とかくこの世は言葉を略す。時間がないのか、仲間内の符丁のようなものか。にもかかわらず、地名を略すのは寡聞にして知らず。尼崎の「アマ」、それ以外に思い浮かぶのは横浜の「ハマ」ぐらいか。「アマ」が広まる理由の一つに、尼崎という地名の長さがあるという。
関西学院大学文学部の元教授で、国語学が専門の大鹿薫久(ただひさ)さん(69)は「尼崎」という地名の長さを挙げる。言語学的には、発音する音の数「拍数」が、地名は2拍か、多くても4拍であるため、ほとんどがそもそも略す必要がない。大鹿さんは「『尼崎』は感覚的に長いと感じる5拍の言葉なので、略称が広まった可能性がある」と指摘する。
横浜の「ハマ」はどうか。
横浜市歴史博物館によると、同市は1909(明治42)年に開港50周年を記念し、市歌と共に「ハマビシ」と呼ばれる市章を決定。この時点で「ハマ」と呼ばれていたようだ。特に海側の地域を指し、港として外国文化が入り交じったエキゾチックな雰囲気などが表現されている、とする。
ただ「アマ」とは異なり、言葉の後ろの部分を残している。大鹿さんによると、警察を「サツ」、新聞屋を「ブンヤ」と呼ぶように、後の言葉を残すのは隠語の場合が多い。「ハマ」も仲間内で呼び習わす隠語の延長にあるという。
隠語ではない「アマ」には、皮肉や親しみなど、広く認知される尼崎のイメージが込められているようだ。

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
三田阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化神戸阪神

-
阪神地方行政

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
スポーツ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神スポーツストークス

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神明石神戸

-
阪神地方行政

-
おくやみ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
新型コロナ姫路阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神タカラヅカ

-
阪神

-
阪神スポーツバレー

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
教育阪神

-
阪神

-
阪神#インスタ

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神バスケ

-
阪神

-
阪神選挙

-
阪神岡崎慎司×兵庫

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神連載阪神

-
阪神

-
選挙神戸阪神

-
阪神

-
LGBT阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
神戸阪神明石淡路

-
淡路阪神神戸東播姫路

-
阪神

-
阪神