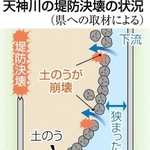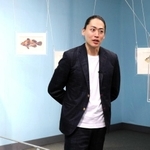太平洋戦争の出征者や遺族らが思い出を語らう講座が、兵庫県芦屋市シルバー人材センター(宮塚町)であった。高齢者の脳を活性化する「回想法」の実践として、市内の傾聴グループ「はつらつコール」が企画。令和を生きる人々に戦争はどのように刻まれているのだろう-。53~95歳の市民約10人が2班に分かれて車座になり、そのうち4人の体験談を聞いた。
「ヒュー」「ドン」
1945年3月12、13日。名古屋城が焼失した名古屋大空襲を経験した三谷千尋さん(83)は、爆弾が落ちてくる時の不気味な音と、その後の地響きが今も耳から離れない。
10メートルほど先に焼夷(しょうい)弾が落ちて、辛うじて無傷で済んだ。縁故疎開をした先では、貨物列車を狙って低空から機銃掃射する戦闘機の米兵と目が合った。
ただ、それ以上に印象に残っているのが国民学校での生活という。先生に会うと必ず立ち止まって敬礼し、「御真影」と呼ばれる天皇・皇后の写真に敬礼した。済むまでは友人とも談笑できず、当時の空気は張り詰めていた。
「日本は絶対に負けないと心の底から信じていた」と話して、こう続けた。
「全員が輪になり、突き進んだのが戦争。今の教育者が戦争に導くことはあってはいけない」
出席者で最年長の河野敬二さん(95)は、千葉県の鉄道連隊に入って国内の鉄道建設に当たった。この日に持参したのは、入隊祝いに多くの仲間が名前を寄せてくれた日章旗だった。
きちんと折り畳んだ旗を取り出す。それを一人で広げると、しばらく何も語ることができなくなった。
「日本のために戦う、その一心で生きてきた」と言う。一方で「上官の言うことが全部正しいとされた」とし、理不尽に多くの命が奪われた戦争への憤りや無念をにじませた。
戦後生まれの瓦谷●一さん(70)の父は南方に出征して帰還したが、亡くなるまで戦争のことは語らなかったという。ある時、父の左脇腹に砲弾の傷が見えても「聞き出す勇気がなかった」と振り返った。
終戦直前に生まれた坂田康子さん(76)は、実父の戦死を物心がついてから知った。「お父さんが生きていたら…」と周囲から頻繁に言われて育ったことが重荷だったとしつつ、「今だから言える」と本音を漏らした。
「一目でいいから、父に会いたいです」(浮田志保)
(注)●は隆の異体字 「生」の上に「一」

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
三田阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化神戸阪神

-
阪神地方行政

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
スポーツ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神スポーツストークス

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神明石神戸

-
阪神地方行政

-
おくやみ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
新型コロナ姫路阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神タカラヅカ

-
阪神

-
阪神スポーツバレー

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
教育阪神

-
阪神

-
阪神#インスタ

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神バスケ

-
阪神

-
阪神選挙

-
阪神岡崎慎司×兵庫

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神連載阪神

-
阪神

-
選挙神戸阪神

-
阪神

-
LGBT阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
神戸阪神明石淡路

-
淡路阪神神戸東播姫路

-
阪神

-
阪神