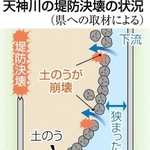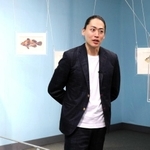高級住宅街として知られる兵庫県芦屋市の宮川河口付近で、海水魚のボラが大量に発生している。黒い影がうごめくのが不気味で、びっくりしてのぞきこむ住民が後を絶たない。水中カメラでのぞくと、うろこが日差しに反射してきらきらと光る。
干潮で水位が下がると海への「帰り道」がなくなり、幅5メートルほどの川を大群が行ったり来たりと大渋滞。ときどき飛んでくるカワウやサギにとってはまさに食べ放題で、しきりにくちばしを水面に突き刺している。
水が引いた川底には100匹以上が取り残され、口をパクパクしている。一部は白い腹を上に向け、沈んで動かない。このときは腐敗臭もなかった。
県西宮土木事務所によると、死因が水質汚染だったり、ボラが積もりすぎて流れが滞ったりと状況が悪化すれば、市などと対応を検討するというが、今の所は「自然の営みの範囲」とする。
地元の「芦屋川に魚を増やそう会」の山田勝己さんは、まだ息があるボラを水中に放り投げて救出しつつ「こんな数は初めて。群れすぎて窒息死してしまったのでしょうか」と心配そうだ。
須磨海浜水族園(神戸市須磨区)の担当者によると、ボラは基本的には海水魚だが、淡水と混じる汽水域にも姿を現し、幼魚の間は敵から身を守るために群れて泳ぐという。
大量発生については「それほど珍しいものではない」としつつ「水温の変動など何らかの要因で川の方が居心地が良いとか、体に着いた寄生虫を落とすためとか、そんな可能性は考えられる」と見立てる。
その上で「まさか潮が引いて海に帰れなくなるとは思わなかったでしょうね」と死んだボラを悼んだ。(大田将之、斎藤雅志、村上貴浩)
◇
■環境研究に一役、食べても美味
阪神間の海で釣りをしていると、ときどきボラがヒットする。糸を巻き上げ、平たい頭が水面に見えてくると「なんや、ボラか…」と少し残念な気持ちになる。釣りでは「外道」の代表格。親からは「くさくて食べられへん」と教えられた。
海や河口に限らず都会の汚れた水路でも平然と泳いでいて、見つけてもなんの感動もない。偏見かもしれないがボラという名前さえ、やぼったく思えてしまう。
理不尽に冷遇してしまっているが、専門家に聞くと意外な一面を知った。
須磨海浜水族園(神戸市)によると、ボラは世界的にもポピュラーな海水魚だという。「日本にいるボラも地中海にいるボラも同じです。だからボラは環境の研究にも使われています」
出世魚で、関西では成長するに連れてハク、オボコ、スバシリ、イナ、ボラ、トドなどと呼び名が変わる。どこにでもいて人々の生活に身近な魚だからこそ、「おぼこいね」「いなせだね」「とどのつまり」といった言葉の語源になっているとの説もある。
さらに驚いたのが、ボラは食べられるということ。寒ボラの刺し身は、とてもおいしいらしい。
藻類や沈殿した有機物をエサとするため、汚れた海では泥臭くなってしまう。ただ、潮通しの良い海や外洋のボラはおいしく食べられるそうだ。冬が旬で、あっさりしながらも脂の甘みが美味だという。
いつも人間のそばでのんびりと泳ぎ、研究にも一役買っていて、実はおいしいボラ。急にありがたい存在に思えてきた。今までぞんざいに扱ってしまっていたことを反省します。すみませんでした。(大田将之)

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
三田阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化神戸阪神

-
阪神地方行政

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
スポーツ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神スポーツストークス

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神明石神戸

-
阪神地方行政

-
おくやみ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
新型コロナ姫路阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神タカラヅカ

-
阪神

-
阪神スポーツバレー

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
教育阪神

-
阪神

-
阪神#インスタ

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神バスケ

-
阪神

-
阪神選挙

-
阪神岡崎慎司×兵庫

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神連載阪神

-
阪神

-
選挙神戸阪神

-
阪神

-
LGBT阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
神戸阪神明石淡路

-
淡路阪神神戸東播姫路

-
阪神

-
阪神