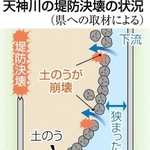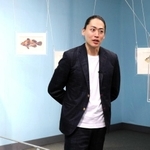夜に井戸から聞こえてくる女の悲しげな声「いちま~い、にま~い…」、で知られる怪談「播州皿屋敷」。兵庫県姫路市に、主人公のお菊を祭る神社のほか、姫路城内にはお菊が投げ込まれたとされる古井戸がある。姫路独自の物語と思いきや、江戸の「番町皿屋敷」など全国に似たような話がたくさんあるという。それは、尼崎にも…。皿屋敷伝説の不思議に迫った。(2017年8月の連載から)
■お菊さん 化身舞う城下町
白鷺の城がそびえる町にひらひらとチョウが舞う。黒い体に鮮やかな紅の紋。ジャコウアゲハだ。
姫路市市制100周年の1989年、市蝶(ちょう)に制定。市花や市木はなじみがあるが、市蝶とは珍しい。
その立役者は、赤松の郷(さと)昆虫文化館(兵庫県上郡町)の相坂耕作館長(69)=姫路市。前年に「播磨の昆虫」を出版、姫路城の伝説との関わりに注目した。「市のシンボルにできないか」。自然保護審議会でその理由をとくとくと説いた。
ジャコウアゲハのさなぎは「お菊虫」。お家騒動に絡む怪談「播州皿屋敷」のヒロインの名だ。さなぎの後ろ手に縛られたような姿を、悪家老らに無実の罪で責め殺されたお菊の化身と見て、そう呼んだ。
「小学校に『お菊神社』を通って行きよったから、興味は昔から持ちよったんです」と相坂さん。
お菊神社が姫路に?
伝説がにわかにリアルに迫ってきた。
■明治期に脚光浴びた“烈女”
姫路城の南西、裏鬼門の地。医薬の神スクナヒコナを祭る十二所神社の境内に、お菊神社はあった。
訪ねた5月6日は「お菊まつり」。氏子が玉串をささげ、浄瑠璃三味線に乗せて「播州皿屋敷」の人形劇が奉納される。伝説は生きていた。
「元々は命日の5月8日やった」と菅原信明宮司(80)。お菊を縛った松の木の断片や縄、具足皿もあったというが、姫路大空襲で焼失した。明治初年の造営とされるお菊神社の再建は1960年のことだ。
由来碑にはこう記されている。
お菊は城主小寺則職(のりもと)に仕え、病気の平癒を祈り、十二所神社に日参。お家横領の密計も探知するが、露見を恐れた逆臣青山鉄山らは小寺家の家宝・赤絵の皿10枚の1枚を隠し、お菊を皿改めの場に引きずり出す。1505(永正2)年、城内古井戸で21歳のお菊は惨死を遂げた-。
意外なことに、お菊の幽霊が足りない皿を数え上げる、芝居や映画で有名なシーンは触れられていない。「明治には、神戸の湊川神社や赤穂の大石神社のように忠臣がもてはやされ、お菊にも光が当てられた」と埴岡(はにおか)真弓・播磨学研究所研究員(63)は推測する。
か弱そうなイメージを覆される。お菊さんは“烈女”なのだ。
■皿屋敷伝説 姫路が源流?
実は、皿屋敷伝説は全国にある。姫路が源流と考えられているのは、1577(天正5)年と最古の年代の文献「竹叟(ちくそう)夜話」があるからだ。
舞台は嘉吉(かきつ)の乱(1441年)で赤松氏を滅ぼした、山名氏の時代。姫路・青山の城代家老小田垣氏は、主君から拝領した五つ組のアワビの杯を一つなくしたと側女(そばめ)に激怒し、松で首をくくらせるが、その影には袖にされた男がいたというものだ。
青山鉄山は伝説上の人物だが、青山の館には山名家重臣で竹田城主となる太田垣氏がいた史実がある。
「播磨の人にとって下克上は強烈なインパクトがあり、新しい支配者への反感があった」と伝説の背景を埴岡さんは読み解く。
江戸の「番町皿屋敷」の悪役の名も架空の青山主膳。姫路がルーツと思いたくなるが、謎は謎を呼ぶ。
播磨出身の民俗学者・柳田国男は「上州妙義山麓の小幡氏一族には、足利時代からの同種口碑がある」と群馬の伝説を指摘する。
ただし、原因は皿でなく飯わんに入った針で、たたりを恐れ菊作りを禁じたという。この小幡氏の末流が1640(寛永17)年、姫路城主松平氏に召し抱えられる。そして、小幡屋敷には墓や菊のタブーがあると文献は伝えているのだ。
お菊の打ち掛けや墓が伝わる福岡の皿屋敷伝説は、菊の恋人が巡礼に出て、播磨に居を定めたとの後日談が興味深い。この伝播(でんぱ)は、福岡藩主黒田氏が小寺氏の家臣であったことによると考えられている。
柳田の言葉を借りれば、伝説とは「類似の伝説を一まとめにし、その異同を比べてみるのが面白い」。
■尼崎、佐用にもお菊井戸
お菊井戸も姫路城だけの名物ではない。
いや、姫路城の井戸こそ正式には「釣瓶取(つるべとり)井戸」。大正時代になって城が一般開放されてから、観光目的で命名されたらしい。
尼崎・大物(だいもつ)の深正(じんしょう)院。ここのお菊井戸は「国道43号で水脈を絶たれるまで、お墓参りに使われていた」と藤野芳雄住職(73)は伝え聞く。
尼崎城主は青山氏。伝説で、女中お菊をあやめて井戸に投げ込む家老は木田玄蕃だが、青山氏の筆頭家老に貴田玄蕃は実在する。1711(宝永8)年、松平氏が城主となると「菩提(ぼだい)寺の深正院を貴田屋敷跡に建てている」と室谷公一・尼崎市教育委員会学芸員(56)は絵図を示す。
1795(寛政7)年、お菊虫が姫路と尼崎の井戸で大発生した騒動の記録が残っているのも意味深だ。
さらに播州の佐用町。国指定史跡の山城利神(りかん)城にもお菊井戸はある。子孫という旧家が位牌(いはい)や墓を守り、芝居を打つ役者が詣でるなど、地域では元祖と信じられていたという。天正年間の出来事とされるが、江戸初期に廃城。皿屋敷は更(さら)屋敷だともいう。草むす姿も、後の世の想像をかき立てたのかもしれない。
皿屋敷伝説とはいわば、普遍的なセクハラ、パワハラの話。「伝説には種があって、ぴたっとくる土壌があると花を咲かせる」と埴岡さん。伝説の点と点をつなぎ合わせると、日本遺産にも匹敵するストーリーが描けそうだ。
■〈余白の余話〉
姫路土産は明珍火箸に「お菊虫」。うそのようだが、志賀直哉も「暗夜行路」で書いている。
どんなものか絵で見ることはできた。川崎巨泉が描いた玩具絵が、姫路文学館の「怪談皿屋敷のナゾ」展にある。でも、実物は残ってないのか。そう思っていたら、あった。「書肆(しょし)ゲンシシャ」のツイッターが画像を上げてくれている。
興味が湧いた向きには姫路の展示は必見だが、会期はきょうまで。お菊さん風に言うと、「あといちにち~(泣)」なのでご注意を。

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
三田阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化神戸阪神

-
阪神地方行政

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
スポーツ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神スポーツストークス

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神明石神戸

-
阪神地方行政

-
おくやみ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
新型コロナ姫路阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神タカラヅカ

-
阪神

-
阪神スポーツバレー

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
教育阪神

-
阪神

-
阪神#インスタ

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神バスケ

-
阪神

-
阪神選挙

-
阪神岡崎慎司×兵庫

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神連載阪神

-
阪神

-
選挙神戸阪神

-
阪神

-
LGBT阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
神戸阪神明石淡路

-
淡路阪神神戸東播姫路

-
阪神

-
阪神