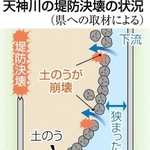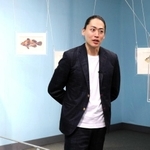4月16日告示、23日投開票の兵庫県芦屋市長選の立候補予定者に、まちの課題や将来像を問う討論会「あしや若者未来トーク」が3月26日、リードあしや(公光町)であった。市内の高校生グループ「あしや部」と神戸新聞阪神総局が共催。立候補を表明している現職・伊藤舞氏(53)▽新人・大塚展生氏(65)▽新人・高島崚輔氏(26)▽新人・中島香織氏(55)-が出席し、「公教育の充実」や「駅周辺の混雑問題」など、若者が考えた六つの質問に対して思いを述べた。質問と回答の要旨は次の通り。(久保田麻依子、村上貴浩)
■同規模自治体に比べて公立中の数が少ない。その要因は公立中に進学する生徒が少ないことが挙げられる。芦屋の公立学校がより魅力的になるために力を入れたいことは。
伊藤氏 近年は公立中学校で自校方式の給食をスタートした。一方、少子化で部活の運営が難しくなっている。新年度から3年間かけ運営のあり方を考える。学生の声もぜひ取り入れていきたい。
大塚氏 中学生の話を聞くと、生徒に寄り添った進路相談の必要性を感じる。また、各中学校にスクールカウンセラーを配置して心のケアに取り組む。地域スポーツクラブの充実も図っていきたい。
高島氏 学校は子どもが豊かに暮らす準備をする場で身近な社会。生活面では校則見直しを生徒と考え、学習面ではAI(人工知能)ドリルなどのICT(情報通信技術)で個人に合った授業をする。
中島氏 市の教育分野については教育委員会が独立して方針を検討する。個人的な意見となるが、教諭の成長が必要だと考える。先生の研修を充実させ、生徒に寄り添って見守る人材育成に取り組む。
■芦屋市は国際文化住宅都市を掲げている。市の持つ国際性のポテンシャルと若者の国際力獲得の必要性をどう掛け合わせるか。
中島氏 市には県立芦屋国際中等教育学校と県立国際高校があり、国際教育に寄与している。成長期に国際的な視点を幅広く持つと、他国への関心が語学や文化・歴史への理解を深め、人としての深みが増す。
高島氏 若者、特に小学校の英語教育を充実させる。海外の学校と姉妹校提携し、オンラインで話す機会をつくる。また、民間の寄付をベースにした奨学金制度を設立し、希望者が留学に行ける環境を整える。
大塚氏 世界の文化に触れる催しや、ディスカッションに力を入れた英語教育を充実させる。芸術面では、芦屋発祥の前衛美術「具体」の作品を通じて海外と交流するなど、多方面から国際性を追求していく。
伊藤氏 コロナ禍以降、オンラインで交流を続けているオーストラリアの学校との修学旅行を実現させたい。阪神間モダニズムで栄えた芸術をさらに発展させていく。地域単位での国際交流も充実させたい。
■阪急芦屋川駅は駐停車で混雑している。特に朝は小学生が通学し危険を感じる。駅周辺の混雑緩和や安全性への具体的な対策は。
伊藤氏 渋滞や危険性は認識している。新年度では、阪急芦屋川駅を挟んだ二つの道路の一方通行化に向けたシミュレーションを行う。歩道を広くしてキッチンカーを置くなど、さまざまな工夫を考える。
大塚氏 歩いてみると、送迎の停車が非常に多く問題だと感じた。駅北側に送迎用のスペースをつくるなどしてみてはどうか。そのためには官民や事業者による協議会を結成し、広く議論する必要がある。
高島氏 スマートフォンで市民から交通情報を寄せてもらうなど、時代に即した交通ニーズの把握が必要だ。長期的には、コミュニティーバスなど自動車に頼らない社会の構築を目指していく必要がある。
中島氏 芦屋川駅では混雑緩和のため駅東側に改札をつくろうという動きもあったが、各々の思惑が絡み調整が困難だった。安全性の確保の観点から何らかの対応が取れないか検討していく必要がある。
■若者の声をまちづくりに反映させるにはどのような方策があるか。また若者の投票率アップに向け、どのような対策を打ち出すか。
中島氏 市民の方が意見や思いを伝えやすい環境を整える。そしてその声を受け止め、一緒に考えていきたい。選挙の1票は必ず皆さんの元に返ってくる。その思いを強く持って投票していただきたい。
高島氏 未来世代の若者が政策提案できる場を設ける。行政はサポート役に回り、「若者扱い」せず徹底的に議論する。まずは身近な校則改革から始め、自分の声で社会が変わる成功体験をしてもらいたい。
大塚氏 米大統領選の事例では、若者が自分ごととして政治に関心を持ち選挙戦に影響を与えた。若者の声を聞くため、市長や若手職員と話を聞く機会を設ける。それが政策のヒントにつながると期待している。
伊藤氏 政治は敷居の高いものだと思われているが、参加することによって社会のルールが決まる。もっと身近に感じてほしい。「1票では変わらない」という思いがあるが、1票は必ず生活に生かされていく。
■なぜ市民が市政に関わることが重要なのか。市民が関わることで何が生まれるか。
高島氏 市政は生活に一番身近で密接に関わるので、市の施策で生活が変わる。結婚や出産など生活の決断は市民がするので、その決断に対する思いに耳を傾けなければ、正しい政策は打てないと考える。
伊藤氏 人口減少が大きな課題で、いかに市民と思いを同じにして、持続可能なまちづくりをするかが重要。タウンミーティングを続けてきたが、課題を捉えて意見を吸い上げ、市民と一緒に物事を進めたい。
大塚氏 例えば、春日集会所の統廃合については住民の声を集約できておらず凍結している。民意あるところに施策ありと考え、住民の希望に耳を傾け、状況に応じて工夫して知恵を出していくことが必要。
中島氏 税金の使い道を決めるのが行政や議会。そこに市民一人一人の声を届け、意見を反映させる仕組みをつくり、できているかをチェックする。本当に市民が主役のまちづくりをするためにはそれが大切。
■あしや部には車いすの学生がいる。芦屋川沿いの歩道はぼこぼこしていて木も多く、車いすの移動が困難。対策をどう考えるか。
高島氏 全ての方が歩きやすいまちをつくることは重要な課題。他自治体にはSNS(交流サイト)で道路のひび割れなどを伝える仕組みがある。皆さんの目を貸していただき、その声を受け取れる仕組みづくりをしたい。
中島氏 茶屋之町や公光町でバリアフリーの対応をしたことがあった。ただ、不十分だったり予算の問題で実現しなかったりした部分がある。再度考えていかないといけない問題として、宿題をいただいたと思う。
伊藤氏 芦屋川の歩道は景観にこだわり土の感覚を残した。土の色のアスファルトを敷く改修を考えており、ユニバーサルなまちづくりを目指す。芦屋もSNSで不具合を報告できるが、周知不足だと反省した。
大塚氏 市民の目線がないと難しいので、SNSで意見を集めるのはいいかと思う。景観も含めてユニバーサルデザインにする。特に車いすの方たちは転倒の危険もあるので、早急に手当をすることが大切。

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
三田阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化神戸阪神

-
阪神地方行政

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
スポーツ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神スポーツストークス

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神明石神戸

-
阪神地方行政

-
おくやみ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
新型コロナ姫路阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神タカラヅカ

-
阪神

-
阪神スポーツバレー

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
教育阪神

-
阪神

-
阪神#インスタ

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神バスケ

-
阪神

-
阪神選挙

-
阪神岡崎慎司×兵庫

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神連載阪神

-
阪神

-
選挙神戸阪神

-
阪神

-
LGBT阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
神戸阪神明石淡路

-
淡路阪神神戸東播姫路

-
阪神

-
阪神