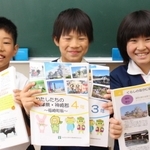寒さが本格化する中、兵庫県上郡町大枝新の千種川河川敷に、スイカの実がなっている。コンクリート護岸の隙間からつるを伸ばし、玉は直径約15センチの大きさに。地域住民は季節外れのスイカを「よう育ったもんや」と見守っている。(伊藤大介)
最初に気付いたのは近くに住む入江紀文さん(80)。川沿いを散歩していた11月中旬、新田橋東岸のたもとで緑色の実を見つけた。当初は「野球ボールくらいの大きさ」だったが、玉は日に日に成長。黒っぽい縞(しま)模様も入り、スイカだと確信した。「水分が少なくても育つもんやけど、まさか冬のコンクリートの護岸でねえ。大したもんや」と目を細める。
さて、そこで二つの謎が浮かび上がる。なぜスイカがコンクリートの護岸に現れたのか。そしてなぜ冬に実が付いたのか-。
同町大枝新の農会長を務める藤田実さん(70)は「スイカ畑を荒らしたハクビシンかアナグマが、河川敷に種が入った糞(ふん)を落としたのでは」とする。実際、近くのスイカ畑で獣害被害が出ていたこともあり、そんな推測にたどりついた。
発芽したコンクリート護岸が「南向きだったことも大きい」と藤田さん。日当たりに恵まれている上、コンクリートブロックの隙間には土が数センチ堆積し、限られた養分で成長を遂げたとみられる。
椎間板ヘルニアの手術を受け、リハビリのために散歩していた入江さんは「大きくなるスイカに元気をもらった。どんな味がするのか、ぜひ食べてみたい」と声を弾ませた。
兵庫県相生市では2005年、路上のアスファルトを破って大根が育ち、「ど根性大根」として全国的に話題を集めたこともあった。

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播姫路文化

-
西播

-
西播

-
西播選挙

-
西播

-
西播

-
西播連載西播

-
西播

-
西播

-
西播神戸

-
西播

-
西播選挙

-
西播

-
西播

-
西播選挙

-
西播

-
西播中学スポーツ中学総体

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播教育

-
西播

-
西播文化

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
姫路西播

-
西播地方行政

-
西播

-
西播文化

-
姫路東播北播西播明石

-
西播姫路

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播連載西播

-
但馬西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播教育

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
新型コロナ神戸姫路西播

-
西播

-
西播東播

-
西播

-
西播連載西播

-
西播

-
西播姫路

-
西播

-
西播

-
西播教育

-
西播選挙

-
西播

-
西播地方行政

-
西播

-
但馬丹波三田阪神姫路西播

-
姫路西播東播

-
西播

-
姫路西播

-
西播

-
西播

-
姫路西播

-
西播連載西播

-
西播

-
姫路西播但馬

-
西播

-
西播

-
西播

-
姫路西播

-
西播スポーツ

-
西播

-
西播

-
姫路西播

-
西播地方行政

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
丹波神戸但馬西播

-
姫路西播

-
西播

-
西播

-
西播