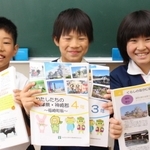「つらら」と言えば地面に向かって垂れるもの、と思っていたが、必ずしもそうではないらしい。兵庫県市川町でこのほど、天に向かって伸びる「逆さつらら」が見つかった。冷え込みが特に厳しかった9、10日、いずれも同じ道路標識の支柱の先に、長さ30~50センチ程度の氷の柱が出現。陽光を浴びてきらめきながら解けていく光景は神々しくもあったが、一体なぜ、こんな現象が起きたのだろうか。(井上太郎)
逆さつららを最初に見つけたのは神河町の奥平辰生さん(68)。9日午後、市川町北部の鶴居地区の県道沿いを車で通り掛かった際に気付き、写真に収めた。「上から水が垂れてくるような場所でもないのに…」。首をかしげた奥平さんは、早速、神戸新聞に情報を寄せた。
夕方、記者が現地に向かった時点では跡形もなく消えていたが、翌日午後に足を運ぶと、そこには再び逆さつららができていた。
奥平さんの写真で見たものよりは少し短いが、制限速度40キロを示す標識の上には細長い氷がすっと伸び、やりのような鋭い先端を青空に光らせていた。
撮影した写真を姫路科学館(姫路市青山)に送って問い合わせると、学芸・普及担当係長の徳重哲哉さん(54)が「珍しいものを見せてもらえました」と、丁寧な回答をくれた。
徳重さんによると、逆さつららは「アイススパイク」とも呼ばれる。原理はやや複雑だが、概略はこうだ。
水は水温4度で最も密度が大きくなり、0度で凍ると密度が下がって膨らむ。このため水面に氷が張ったとき、氷の下の水温が0~4度の間だと、冷えるにつれて水は膨張。この水圧で表面の氷にひび割れが生じるか、あるいは水のたまった構造物と氷との間に隙間があると、そこから水が上に抜けて凍り付き、アイススパイクができることがある。
今回の道路標識のケースでは支柱の背が高く、上端の様子を詳しく確認することはできなかったが、例えば支柱の先に雨水や雪解け水がたまるようなスペースがあり、かつ(1)ふたで覆われているが一部破損している(2)氷がふたのように張っていて、日なた側が先に溶けて薄くなった箇所が突き破られた-などのきっかけで、逆さつららが現れた可能性がある。
神戸地方気象台の福崎観測所では、9日の最低気温が氷点下7・1度、10日も氷点下5・4度と連日冷え込んだ。気象と支柱の構造が偶然、発生条件を満たしたのだろう。奥平さんは「最初はアンテナでも付けられたのかと思った。不思議なことがあるもんですね」と話していた。

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播姫路文化

-
西播

-
西播

-
西播選挙

-
西播

-
西播

-
西播連載西播

-
西播

-
西播

-
西播神戸

-
西播

-
西播選挙

-
西播

-
西播

-
西播選挙

-
西播

-
西播中学スポーツ中学総体

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播教育

-
西播

-
西播文化

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
姫路西播

-
西播地方行政

-
西播

-
西播文化

-
姫路東播北播西播明石

-
西播姫路

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播連載西播

-
但馬西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播教育

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
新型コロナ神戸姫路西播

-
西播

-
西播東播

-
西播

-
西播連載西播

-
西播

-
西播姫路

-
西播

-
西播

-
西播教育

-
西播選挙

-
西播

-
西播地方行政

-
西播

-
但馬丹波三田阪神姫路西播

-
姫路西播東播

-
西播

-
姫路西播

-
西播

-
西播

-
姫路西播

-
西播連載西播

-
西播

-
姫路西播但馬

-
西播

-
西播

-
西播

-
姫路西播

-
西播スポーツ

-
西播

-
西播

-
姫路西播

-
西播地方行政

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
丹波神戸但馬西播

-
姫路西播

-
西播

-
西播

-
西播