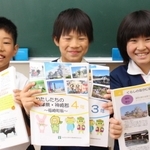奈良・法隆寺に伝わる国宝「玉虫厨子(たまむしのずし)」を、現代の技術で再現するプロジェクトに、兵庫県たつの市の塗師(ぬし)・岡田道明さん(63)ら職人4人が取り組んでいる。単なる模造ではなく、独自の意匠も取り入れるといい「ベテラン職人たちの集大成にしたい」と意気込んでいる。(直江 純)
玉虫厨子は仏像を納めるための漆塗りの台で、歴史書には推古天皇が所有したとの記述もあるが、実際にはもう少し後の7世紀半ばの作と推定されている。光沢の美しいタマムシが装飾に使われたことからその名が付き、朝鮮半島からの渡来人の技術が盛り込まれている。
岡田さんは「玉虫厨子はお釈迦(しゃか)様の教えの神髄を表している。自分たちでも作ってみたい」と1年前に提案。宮殿(くうでん)師の奥居隆夫さん(75)=姫路市、彫金師の國重憲生(のりお)さん(74)=同、蒔絵(まきえ)師の坂根龍我(りゅうが)さん(65)=滋賀県彦根市=の3人と分業することにした。
本物は高さ約2・3メートル。今回は2分の1のサイズを検討したが、ベースとなる木地を担当する奥居さんは「単に縮小するとバランスが悪くなる」と試行錯誤。「一度図面にしてみたが納得がいかず、自分の感覚で書き直したので『だいたい2分の1』です」と語る。
また、実物は屋根の両端にあったはずの懸魚(げぎょ)が失われており、奥居さんが意匠を凝らして再現。昨年末には白木の厨子が形になった。今後、漆塗りを担当する岡田さんは「奥居さんのセンスは抜群。安心してお任せできた」と話す。
塗りは「漆黒」の表現通り、黒色を塗りの奥に閉じ込めるような技法にするという。一方、きらびやかなタマムシの外羽は砕かずに1枚ずつ周囲に埋め込み、色の対比を表現する。
全体の完成は1年後を予定。岡田さんは「機械がない飛鳥時代の本物に、現代の技術と工夫でどこまで勝負できるか。博物館に飾っても恥ずかしくない仕上がりにしたい」と抱負を語った。

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播姫路文化

-
西播

-
西播

-
西播選挙

-
西播

-
西播

-
西播連載西播

-
西播

-
西播

-
西播神戸

-
西播

-
西播選挙

-
西播

-
西播

-
西播選挙

-
西播

-
西播中学スポーツ中学総体

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播教育

-
西播

-
西播文化

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
姫路西播

-
西播地方行政

-
西播

-
西播文化

-
姫路東播北播西播明石

-
西播姫路

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播連載西播

-
但馬西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播教育

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
新型コロナ神戸姫路西播

-
西播

-
西播東播

-
西播

-
西播連載西播

-
西播

-
西播姫路

-
西播

-
西播

-
西播教育

-
西播選挙

-
西播

-
西播地方行政

-
西播

-
但馬丹波三田阪神姫路西播

-
姫路西播東播

-
西播

-
姫路西播

-
西播

-
西播

-
姫路西播

-
西播連載西播

-
西播

-
姫路西播但馬

-
西播

-
西播

-
西播

-
姫路西播

-
西播スポーツ

-
西播

-
西播

-
姫路西播

-
西播地方行政

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
丹波神戸但馬西播

-
姫路西播

-
西播

-
西播

-
西播