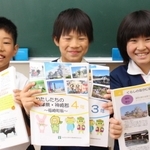赤穂四十七士の間喜兵衛(はざまきへえ)が吉良邸討ち入りの際、やりの柄に付けていたと伝わる自筆の短歌の短冊などが赤穂大石神社(兵庫県赤穂市上仮屋)に寄贈された。短歌には討ち入りに命を懸けた心情が宿る。同神社の義士宝物殿で12月1日から一部を展示する。(坂本 勝)
間喜兵衛は赤穂藩の勝手方吟味役。長男十次郎、次男新六郎と親子3人で討ち入りに加わった。幕府の命で切腹し、3人はそれぞれ69歳、26歳、24歳で生涯を閉じた。
寄贈したのは川西市の福田正博さん。喜兵衛の次女「とも」が嫁いだ福田家の子孫に当たる。先祖伝来のやりや脇差しなど約20点を寄贈し、うち5点は間家伝来の品であると同神社が確かめた。
喜兵衛の短冊(縦30センチ、横5・5センチ)には「都鳥いさ事とわんもののふのはちある世とは知るやしらすや」としたためられている。「都鳥よ、おまえに聞きたい。武士の恥ある世を世間は知っているのだろうか、知らないのだろうか」という意味で、ほかに元赤穂藩士で柔術家の平野半平が十次郎に与えた武道心得(1698年)などがある。
喜兵衛の短歌の短冊は「とも」が嫁いだ際、福田家に持参し、姉婿の中堂又助から贈られたとみられる。
飯尾義明宮司は「討ち入りから離脱した藩士を念頭に、武士の一分を問うた喜兵衛の短歌は感慨深い。貴重な遺品を奉納いただいた」と感謝した。宝物殿は入館料450円。同神社TEL0791・42・2054

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播姫路文化

-
西播

-
西播

-
西播選挙

-
西播

-
西播

-
西播連載西播

-
西播

-
西播

-
西播神戸

-
西播

-
西播選挙

-
西播

-
西播

-
西播選挙

-
西播

-
西播中学スポーツ中学総体

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播教育

-
西播

-
西播文化

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
姫路西播

-
西播地方行政

-
西播

-
西播文化

-
姫路東播北播西播明石

-
西播姫路

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播連載西播

-
但馬西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播教育

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
新型コロナ神戸姫路西播

-
西播

-
西播東播

-
西播

-
西播連載西播

-
西播

-
西播姫路

-
西播

-
西播

-
西播教育

-
西播選挙

-
西播

-
西播地方行政

-
西播

-
但馬丹波三田阪神姫路西播

-
姫路西播東播

-
西播

-
姫路西播

-
西播

-
西播

-
姫路西播

-
西播連載西播

-
西播

-
姫路西播但馬

-
西播

-
西播

-
西播

-
姫路西播

-
西播スポーツ

-
西播

-
西播

-
姫路西播

-
西播地方行政

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
丹波神戸但馬西播

-
姫路西播

-
西播

-
西播

-
西播