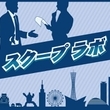プロレスは、生きざまを見せるエンターテインメントだ。レスラーたちは栄光と挫折に感情をむき出しにし、観客たちは、自らの人生と重ねて感情移入する。神戸を拠点に活動するプロレス団体「ドラゴンゲート」には、さまざまな背景を持つレスラーがいる。低身長だったり、複雑なバックボーンを持っていたり。彼らがリングで闘う理由とは何か。それぞれの生い立ちやキャリアからひもといていく。(大橋凜太郎)
ドラゴンゲートの最高顧問、ウルティモ・ドラゴンさん(55)の愛称は「校長」だ。身長を理由に大手プロレス団体から入門拒否された経験をものともせず、メキシコで成功した。世界のファンの心をつかみ、養成学校をつくって多くの門下生を育てた「校長」。そんな不屈の精神を持つ男が、実感を込めて語る。「最近気づいたけど、プロレスラーって頭のねじが2、3本飛んでるよね」
プロレス番組が、テレビのゴールデンタイムで放送されていた少年時代。アントニオ猪木さんらに憧れたプロレス少年が、夢を職業にしようとするのは自然な流れだった。高校卒業後、満を持して新日本プロレスの門をたたいたが、身長が足りないことを理由に不合格を告げられた。
納得できなかった。プロレスラーが全員身長190センチ以上あるなら諦めもつく。でも、低身長で活躍しているレスラーもいる。「自分にできない訳がない」。新日本の関係者に頼み込み、道場に住み込まずに練習に参加する「通いの練習生」としての立場を得て鍛錬した。そして今度は試合会場にいたプロレスの本場、メキシコの団体関係者に直談判。憧れの国に渡るチャンスを得た。
不安はなかった。見ていたのは、トップ選手になる未来のみ。「世界チャンピオンのベルトを巻く」との思いは、目標ではなく、確信だった。その通りに、メキシコの団体でデビューし、1年2カ月後には世界王座を獲得した。その後、日本や米国へと舞台を移した。ロープの反動で回転し、空中から攻撃する得意技「ラ・ケブラーダ」は、その本名にちなんで「アサイ・ムーンサルト」と呼ばれるまでになった。
後進育成のため1997年、メキシコで養成学校「闘龍門」を開校。身長制限は設けず、かつての自分のように志ある若者が来れば迎える環境を整えた。見るからに弱い教え子には「最弱のレスラーを目指せ」と諭すなど、一人一人を大切にプロデュースした。
日本での活躍の場を整えようと、99年にはプロレス団体「闘龍門JAPAN」を旗揚げした。2004年に同団体を改称して誕生したドラゴンゲートでも、教え子たちがリングで躍動している。「今、素直に思えるのは、後輩をたくさん育てて良かったということ」。活躍した選手は数多くいるが、自分よりも後進を育てた人はいない、という自負がある。「校長」はそれを「財産」と表現する。
「後輩にも同じ経験をしてほしいだけ。だって、俺の人生がこんなにも素晴らしいんだから」