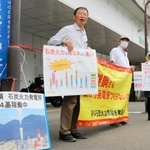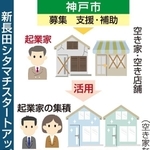坂道を上ると、青々と葉を広げる樹齢約三百五十年のムクノキが迎えてくれる。神戸市の指定天然記念物。高さ十六メートルで市内最大という。クスノキ、エノキ、アラカシなども茂る広さ約二千九百平方メートルの森は、重厚な造りの本殿、拝殿を包み込む。
地元産の御影石を敷き詰めた参道。小鳥のさえずりが響く中、歩みを進めるうちに心が安らいでいく。
この地で、神功皇后が戦勝を祈って熊野大神を祭り、弓と甲(かっ)冑(ちゅう)を納めたと伝わる。「弓(ゆ)弦(づる)羽(は)」の名に引かれ、弓道に励む学生や管弦楽奏者も全国各地から参拝に訪れるという。御影地域八地区のだんじりを繰り出す男衆の晴れ舞台でもある。
長い歴史の中で神社に転機をもたらしたのは、一九九五年の阪神・淡路大震災。社務所が全壊し、鳥居や灯ろうも崩れ落ちた。「復興には、だんじりの祭りで培ったコミュニケーションの力が生きた」と同神社の澤田政泰宮司(54)。倒壊物の撤去などに、氏子らが力を尽くした。
その年の秋には、被災地の復興などを願い、全国から集めた古着一万着で縄を編み上げるプロジェクトが境内で始まった。地元出身の芸術家の提案。直径一メートル、高さ八メートルの大縄は、氏子らが自力で垂直に立ち上げて設置し、震災から丸一年の日に燃やして鎮魂の送り火とした。
「震災から立ち直る中で、氏子同士のきずなが強まった」と澤田宮司。「だんじりだけなく文化活動も」と、毎年夏には地元の小中学生が披露する薪能を開く。
東灘から離れざるを得なかった人もいる。街並みも変わった。澤田宮司は「でも、生まれ育った街のシンボルが変わらずにあることの大切さを思います」。復興を見守ってきた鎮守の森が風に揺れた。
(小林伸哉)
〈メモ〉 5月3、4日は春季大祭・地車(だんじり)祭でにぎわう。1、8、11月以外の第2日曜は茶を楽しむ月釜(千円)。弓弦羽神社TEL078・851・2800
〈アクセス〉 阪急御影駅下車、南東へ徒歩約2分。
【2008年11月24日掲載】

-
神戸

-
神戸

-
文化神戸

-
文化神戸

-
神戸社会連載まとめ読み

-
神戸#インスタ

-
神戸地方行政

-
但馬神戸

-
スポーツ神戸#インスタ

-
教育神戸

-
神戸教育

-
神戸

-
文化神戸神戸ジャズ100年

-
神戸社会連載まとめ読み

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
地方行政神戸

-
神戸新型コロナ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸山口組分裂騒動

-
神戸

-
文化神戸阪神

-
神戸

-
神戸

-
神戸中学スポーツ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
文化神戸

-
スポーツヴィッセル神戸

-
神戸

-
西播神戸

-
神戸

-
神戸防災

-
神戸ウクライナ侵攻#インスタ

-
神戸

-
神戸中学スポーツ中学総体

-
神戸文化

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
文化神戸

-
神戸

-
神戸ヴィッセル#インスタ

-
神戸医療

-
三田選挙地方行政神戸

-
神戸地方行政

-
神戸新型コロナ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸三宮再整備スクープラボ

-
神戸

-
神戸スクープラボ

-
神戸未来を変える

-
防災神戸

-
防災神戸

-
神戸

-
神戸地方行政

-
神戸地方行政

-
神戸

-
文化阪神明石神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸スポーツ

-
神戸

-
神戸

-
スポーツ神戸

-
神戸神戸空港

-
神戸

-
神戸スクープラボ

-
神戸

-
神戸

-
神戸

-
神戸#インスタ

-
神戸淡路

-
文化神戸

-
神戸

-
神戸

-
教育神戸

-
神戸

-
神戸スクープラボ

-
神戸地方行政

-
神戸

-
姫路神戸

-
神戸

-
神戸

-
MARUDORI神戸