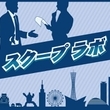戦国時代に三木城主・別所長治と羽柴秀吉の間で争われた三木合戦。兵糧攻めの末、領民の命と引き換えに自害した別所長治の逸話は今も兵庫県の三木市民に受け継がれ、さまざまな行事が行われている。一方、三木合戦で戦死した羽柴方の武将・谷大膳の供養も市内で続いている。地元にとって「敵方」の武将をしのぶ理由は何か。(長沢伸一)
三木市大村の山裾に五つの墓が並ぶ。うち一つは石の門や石柱に囲まれ、立派なたたずまいだ。ここに三木合戦で戦死した羽柴方の武将・谷大膳が眠っている。
大膳は美濃国(現岐阜県)の生まれで、斎藤道三、織田信長に仕えた。三木合戦に出陣し、平田山のとりでを守っていた。
三木城を落とすため、兵糧攻めに出た羽柴方に対し、別所氏や支援する毛利氏が補給路確保に向けて平田山のとりでを急襲した。攻め込まれた大膳は大なぎなたを振るって奮戦したが戦死。合戦後、秀吉は大膳を弔い、大膳と兄弟らの墓を大村に建てたとされる。
墓は現在、地元住民でつくる「善友会」が維持・管理している。毎年8月1日には墓所を清掃し、手を合わせて供養している。だが、敵方の武将である大膳の供養が行われている理由は判然としない。同会の栗田恒男会長(80)は「私もなぜ供養されてきたのか不思議に思っている」と首をかしげる。
◇
大膳の位牌(いはい)は金剛寺(大村)にある。墓での供養も毎年、同寺の住職が読経している。
供養の理由について、福岡心明住職(42)も「よく分かりません。金剛寺は三木合戦の時に羽柴方の手で燃やされているんです」と不思議がる。同寺は、合戦の際、焼き打ちで仏像数体以外は焼失したとされ、そばの平田山のとりでにいた大膳は、寺を焼いた実行役の可能性があるという。
福岡住職は「私見」と前置きした上で、江戸時代の古文書などを基に解説してくれた。
大膳の息子が初代藩主となった丹波・山家藩の資料には「『付近の人其(そ)の武勇を慕ひし焼香絶えず』とあり、江戸時代から多くの周辺住民が大膳の墓参を行っていたんです。合戦後に三木が復興していく過程において、戦死者の敵味方にとらわれず、供養して平穏を祈ったのではないでしょうか」
では、寺を焼いたかもしれない武将の供養を金剛寺がなぜ担っているのか。福岡住職は、秀吉の命令▽宗派と祖先の関係(同寺の所属する真言宗御室派は宇多法皇を祖とする。谷家も宇多法皇を祖先とする宇多源氏の支流)▽戦死した場所から最も距離が近い寺-の3点を挙げる。
特に秀吉の命令に関しては、焼失した金剛寺を復興する際、同寺の塔頭(たっちゅう)寺院出身の大村由己(秀吉の右筆で、秀吉の活躍を記録した軍記物『天正記』の著者)が、秀吉に再興を願い出た書状が現代に伝わっている。福岡住職は「寺再建の条件の一つとして大膳公の供養が課せられたのではないか」と推測する。
以降、江戸時代を通して、供養は命日に毎年営まれ、山家藩からも藩士が参拝した。その後も藩や筆頭家老の福田家と寺とのやりとりが確認できるという。
◇
今年の8月1日。善友会のメンバー6人が大膳の墓を清掃した。草を刈り、花を供える。福岡住職の読経が響く中、墓に線香を供えて手を合わせた。福岡住職は言う。「正確な経緯は分かりませんが、敵味方を問わずに供養することを400年続けているのは三木が誇れることなのではないでしょうか」