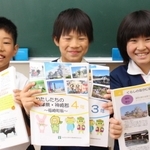■小惑星の砂、放射光で分析
5200000000000メートルもの長旅で得た石を、0・000000001メートルの単位で調べたという。とてつもない桁数はまさに「天文学的」と呼ぶに値する。
長い方は52億キロメートル。宇宙航空研究開発機構(JAXA)の探査機「はやぶさ2」の飛行距離だ。目的地の小惑星「りゅうぐう」までは直線でも約3億キロ超。地球と太陽の距離(約1億5千万キロ)の倍にあたる。
短い方は1ナノメートル(10億分の1メートル)。新型コロナウイルスの直径が100ナノメートルほどという。兵庫県佐用町、上郡町、たつの市にまたがる大型放射光施設「スプリング8」では、医療用エックス線の1千万倍以上の強い光で物質を分析できる。
はやぶさ2は2014年に打ち上げられ、19年にりゅうぐうへの着陸に成功。岩石をカプセルに封じ込め、20年に地球に帰還させる「サンプルリターン」に成功した。
りゅうぐうには太陽系が生まれた約46億年前の水や有機物があると期待されていた。地球の水はどこから来たのか。生命につながる有機物はどこで作られたのか。サンプルは謎を解く「玉手箱」に例えられた。
スプリング8では、その帰還を2人の「ウエスギ研究員」が待ち構えていた。施設運営を支援する「高輝度光科学研究センター」の上杉健太朗さん(49)と上椙真之さん(49)だ。
「二度と手に入らない、絶対に汚せないサンプル。とてつもない重圧だった」。上椙さんは21年6月、長手袋状の器具「グローブボックス」越しに岩石を分析した。大気や細菌など地球上の全物質が「触れてはいけない汚れ」なのだ。
一方の上杉さんは器具の設計を得意とする。小さなサンプルを固定する針は極細のチタン製。真空を保つ運搬容器は佐藤精機(姫路市)と何度も試作を繰り返した。
コンビが支援した東北大などの研究チームは、りゅうぐうの砂の中に「密閉された穴がある」ことをスプリング8の画像解析で確認。その中に微量の炭酸水があることも判明した。
2人は「太陽に近いと炭酸水は残らない。りゅうぐうがもっと遠くにあった証拠です」と解説する。「地球の水は小惑星が衝突してもたらした」との仮説を補強する大発見だった。
「初代の時は苦労したから。今回は準備万全でしたよ」と上杉さん。初代探査機「はやぶさ」は通信途絶のドラマが注目されたが、小惑星「イトカワ」のサンプル分析も苦難の連続だった。上椙さんも当時JAXAに在籍し、スプリング8に通ってタッグを組んでいた。
2人の今後の大仕事は、火星で採取される予定のサンプル。「りゅうぐうが玉手箱なら、火星は『パンドラの箱』かもしれない」と上椙さん。「『宇宙検疫』の体制が必要になる」と気を引き締める。
火星には液体の水が存在するとみられる。地球外生命の発見へ期待が高まる一方で、人体や生物に害を及ぼす未知の病原体が飛び出してくるかもしれない。「何かを達成したら、次はまた桁違いの難度が求められちゃうんだよな」。2人の果てしない物語は続く。
【バックナンバー】
<4>惑星命名 私設観測所で次々発見
<3>光害 「暗さ」逆転の発想で強みに
<2>花北観望会 星空のロマン伝え20年
<1> 星空案内人 「宇宙講座」で天文ファン獲得
<プロローグ> 宇宙研究の拠点集まる西播磨

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播姫路文化

-
西播

-
西播

-
西播選挙

-
西播

-
西播

-
西播連載西播

-
西播

-
西播

-
西播神戸

-
西播

-
西播選挙

-
西播

-
西播

-
西播選挙

-
西播

-
西播中学スポーツ中学総体

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播教育

-
西播

-
西播文化

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
姫路西播

-
西播地方行政

-
西播

-
西播文化

-
姫路東播北播西播明石

-
西播姫路

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播連載西播

-
但馬西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播教育

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
新型コロナ神戸姫路西播

-
西播

-
西播東播

-
西播

-
西播連載西播

-
西播

-
西播姫路

-
西播

-
西播

-
西播教育

-
西播選挙

-
西播

-
西播地方行政

-
西播

-
但馬丹波三田阪神姫路西播

-
姫路西播東播

-
西播

-
姫路西播

-
西播

-
西播

-
姫路西播

-
西播連載西播

-
西播

-
姫路西播但馬

-
西播

-
西播

-
西播

-
姫路西播

-
西播スポーツ

-
西播

-
西播

-
姫路西播

-
西播地方行政

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
西播

-
丹波神戸但馬西播

-
姫路西播

-
西播

-
西播

-
西播