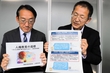クマによる人的被害は2023年度に過去最多となり、環境省はクマを「指定管理鳥獣」に追加し、対策強化に乗り出した。各自治体は、手が回らなかった個体数調査や捕獲に国の交付金を充てる見通しだが、過度な捕獲によりクマが減少することへの懸念もある。担当者は「被害対策と保全の両立は難しいが、共存を目指したい」と話す。
■バランス
「必要な捕獲が計画的に実施できる」。2月、環境省の専門家検討会。委員の一人は、指定により交付金が支給され、自治体がモニタリングや実施計画に基づき捕獲できることにメリットがあると説明した。
環境省によると、23年度のクマの人的被害は、統計のある06年度以降最多の198件、219人(うち死者6人、速報値)だった。捕獲数も9319頭(24年2月末までの速報値)で、08年度から残る同種統計の過去最多を記録した。
住民の安全を確保しながら、クマとのすみ分けをどう図るか。個体数や生息分布などの調査やモニタリングの重要性は一層増している。しかし、対応は自治体に委ねられ、頻度や精度はまちまちなのが実態だ。
生息数2800~6千頭と推計される秋田県では、23年度の人的被害が速報値で62件70人と全国最多となった。
県によると、捕獲上限数を設定したり、捕獲する対象を人里に現れたクマに限定したりして保全を図ってきたが、23年度は夏ごろから人里での出没が多発した。県は負担が増したハンターらに支援金も支給したという。捕獲数の上限とした1582頭の超過も認め、速報値で約2300頭が捕獲された。
県の担当者は「人命に対するリスクを踏まえた。保全とのバランスが崩れていないか調査で確かめ、詳細な生息数を把握して改めて捕獲のルールを設定したい」と語る。
秋田県は17~19年度に行った自動撮影カメラによる調査を再開する方針で、担当者は国の交付金の活用を期待する。
■場当たり的
交付金により個体数調査の正確性を確保したいという自治体もある。酪農学園大の佐藤喜和教授(野生動物生態学)は、予算不足の自治体の駆除や保護は場当たり的だったとし、国の支援を受けることで「適切なモニタリングに基づく対策が可能になる」と指摘。「人里近くにいるクマは減らす必要があるが、個体数や農業被害を調べ、捕獲数や対策を見直すことも重要だ」と強調した。
◇
兵庫県森林動物研究センター(丹波市)によると、23年度、県内ではクマによる人身被害は発生しなかった。しかし、同年度に県内で報告されたツキノワグマの目撃・痕跡発見情報は524件に上り、住民に不安が広がっている。
個体数は近年横ばい傾向とみられるが、生息域は氷ノ山(養父市)周辺から丹波、播磨地域に拡大しているという。
同センターの担当者は「クマに遭遇しないよう対策を講じることが大切。山に入る時は鈴を付けたり、大人数で行動したりしてほしい」と呼びかけている。