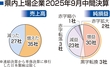今年から来年にかけて「阪神・淡路大震災から30年」という標語が主にマスコミで使われている。一見すると問題のない表現のようにみえるが、私が東日本大震災の調査をしていた時に、ある遺族の方は、震災発生から10年を過ぎた頃から、「東日本大震災から10年」という区切りで報道されることに強い怒りを表明されていた。なぜだろう。
この表現は、震災がすでに10年前に終わっていて、残余として災後があり、初めから震災を風化させる意図があるという違和感の表明である。とりわけ大切な人が亡くなった当事者家族にとっては、いまだ震災の真っただ中にあり揺れ続けている。震災は終わったかのように言われるが、いまだ過ぎ去っていない現在進行形の課題なのである。
仮に当事者が大丈夫だと思っていても、今年起きた能登地震の際に正月に帰省した先で被害に遭う出来事が、阪神・淡路で帰省した時に被災し息子さんを亡くされたことと重なり、大丈夫だと思っていた自分が再びトラウマの渦へと引き戻される方もいた。大震災は彗星(すいせい)の尾のごとく、人々の心に痕跡を残して揺さぶり続けている実態がある。
■体験の共有化と語り継ぎ
他方、もうひとつの現実問題として、あの出来事から誰しもが30年の時間を経過したことは30歳年齢を重ねたか、未災の経験者を含め震災を知らない世代が増えることを意味する。2021年には神戸市で震災を経験していない市民が5割に達したとの報道があった。いわゆる「30年限界説」問題である。たとえば教育の現場で初期の頃は誰もが震災の経験者だったが徐々にその数が減り、定年を迎えたりそれを伝える側の人員が確保できなかったりする問題が挙がっている。そこで重要になってくるのが、次の世代への「語り継ぎ」という取り組みである。
12月に第10回全国被災地語り部シンポジウムが神戸で行われた。多世代の語り部の報告がなされたが、そのなかでも若い語り部が一堂に会して災害を経験していない人たちが語る価値や悩みについて議論が熱く交わされた。
ここでは震災を直接体験していない若い世代からの創意工夫が現場から上がってきている。というのも体験者の語りを100%まねて伝えるやり方では、正確に伝えることに加えてその場にいないこともあって語り手に大きな心理的負担を強いることになる。それに対してとりわけ若者が語り継ぎを試行した際には、体験そのものをコピーすることを能力の点からも諦め、第1次体験者の語りから本人(伝え手)が感じたことを聴衆に向けて共有化しようとするケースが少なくない。この取り組みは震災は経験したものでないと分からないとする生の体験とは異なる語りである。
語り継ぎは、いわば「翻訳」に例えることができる。能楽師の安田登さんが『ウェイリー版・源氏物語』のなかで、異化翻訳と同化翻訳とに分けてとりわけ後者に着目している。異化翻訳は、できるだけ原文に近い形で異質な文化を異質なまま翻訳する方法である。他方同化翻訳は、他国の文化コードに合わせて受容する方法である。1000年前の源氏物語は異化翻訳でたとえば部屋の間仕切りにあたる几帳はそのままkichoと使われているがほとんどの人は理解できない。光源氏という言葉もそのままでは古典に習熟してないと分からない。ところがウェイリーさんが翻訳をしたものは、同化翻訳にあたるもので、几帳はカーテン、光源氏はシャイニング・プリンスと、今の私たちにとってとてもなじみのある言葉に置き直されて誰しもがイメージしやすくなるのである。
この同化翻訳は語り継ぎにも当てはまるのではないだろうか。伝える側は、自分は経験していないが、あのときの震災を経験していないがゆえに聞いている聴衆の気持ちに素直に寄り添う形で語ることができるのである。ともすれば伝承する側とされる側には、どうしても落差が生じてしまう。このような熱意の差があると、活発に意見を交換することはおろか、伝えられる側はただ黙って他人事として聞くようになってくる。その落差を埋めて、他人事の災害を自分事にするために同化翻訳的語り継ぎの意味は大きい。
災害という私たちの日常世界とあまりにも隔絶したことを伝えるという意味においては異化翻訳的な語りで未災者にそのまま伝えることはとても大切なことである。究極的には自分が受けた痛みは分かりえないということを言葉として伝えようとする。他方誰にでも開かれているという形で、聞き手に共有化し分かるようにしようとする同化翻訳的な語り継ぎもまたほそぼそとした取り組みではあるが意義は大きい。
30年という月日がたつ中で両者の考え方はかなりの隔たりがあるといえる。しかし私たちがどちらかに重み付けを行うのではなく、どちらの取り組みも災害を次世代に伝える点においてともに重要であるという心持ちがこの神戸を中心とした阪神・淡路大震災の地で問われているのではないか。
(かねびし・きよし=関西学院大社会学部教授、災害社会学)