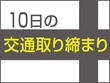豊岡市で取り組まれてきた国の特別天然記念物コウノトリの野生復帰事業で、2005年9月に人工繁殖させた個体を初めて放鳥してから20年が過ぎた。自然繁殖などの結果、野外の生息数は550羽を超えた。繁殖地は関東から九州にまで広がり、今年は13府県で巣立ちが確認されている。兵庫県内でも繁殖地が増え、播磨などでは数十羽単位の群れとなっている。
一度絶滅した生物を人が育てて増やし、自然に戻す困難な試みは世界の注目を集めてきた。5羽から始まった放鳥が大きな実を結んだことは、地元として誇らしい。
コウノトリは日本各地にいたが、明治期以降、乱獲や農薬などで激減した。最後まで繁殖地が残った豊岡市での保護活動は70年前にさかのぼる。保護協賛会(保存会)が発足し、1965年に野生のつがいを捕獲して「保護増殖」を始めたものの、71年に最後の1羽が死んだ。
しかし85年に旧ソ連から贈られた幼鳥6羽で改めて繁殖に取り組み、ひなの誕生を成功させた。繁殖は順調に進み、初放鳥につながった。県立コウノトリの郷(さと)公園元飼育長の松島興治郎さんは「500羽余りを数える状況は感慨深い」と話す。今の生息拡大は、多くの関係者の努力があってこそ実現した。
復帰を支えたもう一つの活動は、生態系を回復させる農業の実践だった。地元農家が営農組合を設立し、農薬や化学肥料に頼らない米作りを始めた。水田はコウノトリの餌場となった。
「コウノトリ育む農法」を行う農地は増え、収穫米はブランドに育った。鳥に安全な環境では人間も安心して暮らせる。生物との共生は、私たち自身のためでもあると意識したい。
ただ課題もある。現在のコウノトリは遺伝子の多様性に乏しく、500羽ではまだ安心できないという。農家の高齢化も進んでおり、農法を継承する次世代の育成が欠かせない。
世界全体では4万7千種以上の生物が絶滅危惧種に当たるとされる。コウノトリの野生復帰に向けた長年の事業は、生物多様性を守り、生態系を維持するモデルになり得る。地域全体で取り組んできた貴重な経験を今後も世界に発信し続けたい。