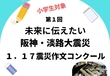政府の地震調査委員会が、今後30年以内にマグニチュード(M)8~9級の南海トラフ地震が発生する確率を見直した。
これまでの「80%程度」から「60~90%程度以上」に変更した。併せて別の計算方法による「20~50%」も示した。過去の地盤隆起データの誤差や予測の不確実性を考慮したためという。数値の幅が大きく、戸惑う自治体や住民らは多いだろう。
今回の見直しは、地震学の限界を示すものでもある。とはいえ、発生すれば兵庫県内を含め広大な範囲で甚大な被害が想定される。調査委の平田直委員長は「いつ起きてもおかしくない状況に変わりはない」と述べている。確率の高低にとらわれず、備えを着実に進めたい。
南海トラフの発生確率は「時間予測モデル」という特殊な計算方法で求めていた。古文書に隆起量が記録された室津港(高知県室戸市)のデータを基に計算してきたが、誤差が考慮されず、別の計算方法をとる他の地震よりも高い数値が出るとの指摘が専門家らから上がっていた。
特殊な計算手法がとられたのは、防災対策の予算を多く獲得したい専門家や行政の思惑があったとの指摘もある。国民に対して誠実な姿勢だったと言えず、猛省が必要だ。
今回の見直しでは、従来の計算方法を踏まえつつ、新たな知見も加えて「60~90%程度以上」と幅を持たせた。隆起量を用いない他地域と同様の計算も行い、「20~50%」を併記した。調査委は「全ての知識を使い科学として最善の方法で示した」と意義を強調した。
調査委は防災上の観点から、住民らに確率値を示す場合は「60~90%程度以上」が望ましいとした。発生確率に基づき地震の危険度を示す指標では、2種類とも見直し前と同じ一番上の「高い」に分類した。
ただ、二つの確率が併記されたことで、複雑で分かりにくくなった点は否めない。これまでの半分以下の数値も示され、警戒感が薄まる懸念もある。政府は見直しの背景や受け止め方について、自治体や住民に丁寧に説明する必要がある。
南海トラフ地震はおおむね100~150年間隔で起きるとされる。直近の昭和東南海地震(1944年)や昭和南海地震(46年)から約80年が経過し、発生が迫っていることは間違いない。
政府は今年3月、M9級の地震が起きた場合、最大で死者29万8千人、経済被害約292兆円に上るとする新たな被害想定を公表した。
現在の科学ではまだ地震を正確に予測できない。その点を踏まえた上で、被害を少しでも防ぎ、減らすための対策を改めて進めるべきだ。