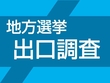20代女性のAさんは、同じ職場で出会ったBさんと結婚しました。職場が同じのため、時間が合うときは一緒に出勤したり、帰るようにしています。そんなある日一緒に帰っていたとき、Bさんが「『お前』って呼ぶのに憧れているんだよね」とつぶやきます。
お前と呼ばれるのに抵抗のあるAさんは「じゃあ私もこれから『お前』って呼ぶね」と返すと、「いやそれは…」とBさんは嫌がりました。どうしてBさんはAさんのことを『お前』と呼びたかったのでしょうか。カップルセラピストの坂﨑崇正さんに話を聞きました。
■「お前」呼びしたい理由は3つ考えられる
ー「お前」と呼びたい理由・背景は何が考えられるのでしょうか?
「お前」という言葉は、本来「御前(おんまえ)」が語源で、もとは敬意を表す言葉でした。しかし現代では、対等・上下・親密など、文脈によって意味が大きく変わります。
そこに込められる心理は、主に3つに整理できます。
1つ目は、親密さや特別感の演出。恋人や夫婦といった「他の誰でもない関係」を象徴する言葉として、「お前」と呼びたい人もいます。呼称を通して「あなたは自分の特別な存在だ」と示し、その意図は決して乱暴さだけではありません。
2つ目は、関係の主導権を感じたい欲求。「お前」と呼ぶことで、無意識のうちに「関係の中での立ち位置」を確かめようとする心理が働くことがあります。それは必ずしも支配したいという意図ではなく、安心の形が“優位性”で表現されてしまうタイプの人に多く見られます。
3つ目は、文化や地域の影響です。特に関西では、幼少期から友人同士で「お前なあ!」と冗談まじりに言い合う文化があり、「お前=親しみを込めた言葉」として育まれてきました。このため、関西出身者の中には、悪意なく“砕けた愛称”として使う人も少なくありません。言葉の温度は、育った地域や家庭の文化に深く影響されるのです。
ーなぜ自分がされて困る・嫌なことを、自分(Bさん)はしても問題ないと考えているのでしょうか?
この矛盾の背景には、いくつかの心理的メカニズムが働いています。
1つ目は、「自分基準の共感」です。自分が心地よい・自然だと感じることは、相手にとっても同じだろうと無意識に想定してしまう。つまり、“自分の感じ方”を一般化してしまうのです。好きなパートナーであれば、なおさら「そうであってほしい」と強く働く傾向にあります。
2つ目は、「親密さと境界の混同」があります。恋人や夫婦関係では、近づきたい思いが強いほど、境界をあいまいにしやすくなります。「親しいのだから、多少踏み込んでもいいだろう」と思ってしまう。それが、“相手の尊重よりも親密さを優先する”という形で現れます。
3つ目は、「二重基準(ダブルスタンダード)の自己防衛」も働きます。自分は相手に親しみを込めて言っているが、相手から同じことをされると“主導権を奪われた感覚”を覚える。これは、親密さを求めながらも、心理的には対等に慣れていない状態を示しています。つまり、「お前」と呼びたい心理の裏には、自分が上に立つことで安心したい心が隠れていることも多いのです。
呼び方そのものが悪いわけではありません。問題は、その言葉が相手にどんな意味で届くかを見極めきれていないことです。「お前」が愛情表現になるか、支配のサインになるかは、文脈と合意、関係性、相手の性格によって変わります。
もし二人の間に違和感が生じたら、「どう呼ばれたい?」「どう呼ぶとしっくりくる?」と、言葉の背景を話し合ってみること。その対話の中にこそ、関係の“対等な特別さ”を育てるヒントがあるのです。
◆坂﨑崇正(さかざき たかまさ)臨床心理士・公認心理師
カップルセラピー専門機関「COBEYA」カップルセラピスト。スクールカウンセラーなど教育機関における相談支援や専門家への指導に従事したのち、現職。現在は主に、トラウマ体験や浮気・不倫などの悩みを抱えるカップルの支援に携わる。
(まいどなニュース特約・長澤 芳子)