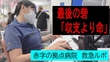11月1日と2日に、神戸市にある商業施設「マリンピア神戸」で、「服の交換会」というイベントが開かれた。
日本では年間約47万トン(2022年)もの服が廃棄されている。「令和4年度 循環型ファッションの推進方策に関する調査業務(環境省)」によると、リサイクル・リユース率は全体の3割程度しかない。地球環境への負荷を少しでも軽減しようと始まった取り組みが、この「服の交換会」だ。
「服を捨てる」という罪悪感から解放されるだけでなく、地球環境にも少しだけ貢献したという満足感も得られるユニークな試みを取材した。
■「着なくなった服は交換する」捨てない選択が環境負荷を減らす
「服の交換会」を主催するのは、加古川市に本社を置く株式会社ワンピース。服飾雑貨の企画、デザイン、製造販売などを行うアパレル企業だ。同社で「服の交換会」ディレクターを務める石田晴也さんに話を聞いた。
「服の交換会を始めたきっかけは、国内で服の廃棄量が年間で47万トンもある現実を、微力ながら改善したいという思いからです」
製造過程や流通システムを見直すことが理想と認識しながらも、すぐ実行に移すことは難しい。製造後の製品で何かできないかと考えた結果、服の循環を促す仕組みとして「服の交換会」がスタートしたという。
「服を捨てず、誰かの手に渡すことで廃棄量を減らせますし、服の寿命も延ばせます」
2021年に始まって以来、商業施設やSDGsをテーマとしたイベントなどで月1~2回ペースで開催されており、今回で50回目を迎えた。
交換会に集まる服は「持ち寄り」のため多種多様で、サイズもバラバラ。そして圧倒的にレディース服が多く、メンズ服はわずかだ。
参加者は、自分が着なくなった服を会場まで持ってきて、他の参加者が持ってきた服から気に入ったものと交換する。その際、持って帰る服の重量を計測する。これは服の重量を温室効果ガスの量に換算して、排出量をどれだけ抑えたかを可視化するためだ。あくまで目安の数値だが、地球環境に配慮しているという意識の啓発になる。
交換は原則として1着に対して1着で、1人5着まで交換できる。その際、交換料として550円をワンピースに支払う。これは輸送費やイベントの運営費などに充てられるという。
参加者は圧倒的に女性が多く、とりわけ子育て世代が目立つ。子供服はすぐにサイズアウトしてしまうため、持ち込まれた服の中にはほぼ新品に見えるくらい状態の良いものが多く見られた。
■課外学習で環境問題を学ぶ高校生も参加
この日は兵庫県内にある高校から、校外活動で環境問題を学ぶ高校生も参加していた。
彼らはフランス発の環境評価ツール「Ecobalyse(エコバリズ)」を用いて、服1着当たりの製造過程における環境負荷を「エコスコア」として数値化。それをタグにして、その服が地球環境にやさしいのか厳しいのかを一瞥して分かるようにしていた。
参加していた高校生のひとり、1年生のS君に話を聞いた。彼は超有名な進学校に通いながら、校外活動で気候変動や健康についても学んでいるそうだ。
「Ecobalyseは素材の原料、例えばレーヨンが何%、ウールが何%という情報や全体の質量から環境負荷の大きさを表す数値を算出します。数字が大きいほど、環境負荷も大きいということです。ただ、基準のひとつにすぎないので、環境負荷が大きい服=悪い服とは考えてほしくありません。着たい服を選ぶときに、環境を思いやる意識をもってほしいと思います」
また、石田さんはこのようにも語る。
「いまの若い世代の子たちは、古着への抵抗感が低いです。高校生が関わってくれることで、この取り組みも世の中に広がりやすいと思います」
今後は、行政との連携を強化し、各地域で交換会を根付かせたいという石田さん。実際に富山県高岡市がSDGsに関して市民に行動変容を起こしたいとのことで声がかかっているそうだ。
また、参加者同士で自然に会話が生まれてコミュニティ化していく現象も起こっており、服の交換を通して人と人とのつながりができていることが想定外の効果として表れているという。
「服の廃棄量が多すぎるから何とかしたい」という思いから始まったイベントは、いまや企業の枠を超えた社会的なムーブメントになりつつある。
(まいどなニュース特約・平藤 清刀)