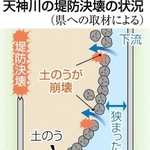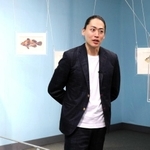■芦屋・芦屋公園 大阪湾潮流の影響で流れ着く?
岩肌にはこう刻まれる。
「ぬえ塚」。関西屈指の高級住宅街で名高い兵庫県芦屋市の芦屋公園に、なぜ妖怪「ぬえ」の墓があるのか。調べると、二つの手がかりが見えてきた。
「ひょー、ひょー」と不気味な声で鳴き、頭はサル、胴体はタヌキ、尾はヘビ、手足はトラの異形の姿。そのルーツは「平家物語」にさかのぼる。
平安時代、近衛天皇の御殿を謎の黒雲が覆ったので、弓の達人源頼政が雲に矢を放った。すると、空からぬえは落ち、丸木舟で川に放たれ、芦屋の浜辺に打ち上げられたという。
なぜ芦屋なのかを知る鍵の一つは能だ。退治後の話は室町時代の能楽師・世阿弥が晩年に作ったとされる謡曲にあり、ぬえは芦屋で亡霊となって僧に成仏を請うという哀れな姿で描かれる。
「自身の境遇に重ねたのではないか」と、芦屋市の能楽師・長山耕三さん(49)は推測する。能を大成した世阿弥は70歳を過ぎて佐渡島に流され、栄光から見放された。「その悲しみを、かつて都で暴れたぬえに寄せた」という説だ。
しかし、芦屋への漂流が完全な創作とは言い切れないとの見方もある。
二つ目の手がかりとして、県立人と自然の博物館(三田市)の研究員大平和弘さん(37)=緑地環境科学=は大阪湾の潮流を指摘する。
淀川の漂流物は河口付近の西宮沖環流で南進し、湾中部を時計回りに流れる沖ノ瀬環流で神戸-阪神間へ流れ着きやすい。西宮神社のえびす信仰は、漂着した木や死体を「えびす」と呼んで海の安全を祈ったのが起源とされ、祭神は海へ流された「国生み神話」のイザナギとイザナミの子だと伝わる。
「芦屋にも漂着物は多かったはず。不可解な動物の死骸が、ぬえに結び付いた可能性もあるのでは」
まさか、ぬえとえべっさんがつながるとは…。えびすが時代を経て、漁業の神、商売の神へと意味付けが加わっていったように、ぬえも進化を遂げている。
芦屋では人々がぬえを手厚く葬ったおかげで厄災を免れたと語り継がれ、昨秋には新型コロナ退散を祈る鎮魂祭がぬえ塚であった。
市役所には地元の小学生らが作った毛むくじゃらのぬえ人形が飾られる。ぬえが市のキャラクターになる日も遠くないかもしれない。
【メモ】芦屋市教育委員会によると、ぬえ塚は江戸時代の地誌「摂陽群談」や「摂津名所図会」で、芦屋川と住吉川の間にあると紹介される。芦屋公園の石碑は昭和初期に作られたらしい。似たような伝承のぬえ塚は大阪市都島区にもある。「ぬえのような」は「得体(えたい)の知れない」を意味する慣用句で知られるが、最近は漫画「呪術廻戦」やアニメ「妖怪ウォッチ」などで多彩な描かれ方をしている。

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
三田阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化神戸阪神

-
阪神地方行政

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
スポーツ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神スポーツストークス

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神明石神戸

-
阪神地方行政

-
おくやみ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
新型コロナ姫路阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神タカラヅカ

-
阪神

-
阪神スポーツバレー

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
教育阪神

-
阪神

-
阪神#インスタ

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神バスケ

-
阪神

-
阪神選挙

-
阪神岡崎慎司×兵庫

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神連載阪神

-
阪神

-
選挙神戸阪神

-
阪神

-
LGBT阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
神戸阪神明石淡路

-
淡路阪神神戸東播姫路

-
阪神

-
阪神