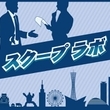健康づくりのためのいわゆる「毎朝登山」は神戸から始まったとされる。ニッカーボッカーにハンチング帽の「異人さん」が六甲山に吸い込まれていくのを目にし、好奇心旺盛な神戸っ子は見よう見まねで登山という名の散歩を始め、やがて全国に広まったという。
洋服、マラソン、ラムネ…。神戸には「日本初」が多い。それは日本人と外国人との交流が盛んだったためだが、神戸大学名誉教授の神木哲男さんによると、その原点は開港当初の居留地の状況にあるという。
神戸は開港や居留地の建物の整備が大幅に遅れた。結果として、本来は居留地に住むべき外国人が区域外に出ることになった。
開港から3カ月後の1868年3月、当時の外交責任者で後に兵庫県知事となる伊藤博文が各国領事宛てに出した書簡が残る。
外国人が日本人から土地や家屋を借りるなどして、一定の範囲で住むことを認める-とする内容だ。
「一定範囲」とは、東は旧生田川から西は宇治川まで、北は六甲山麓から南は海まで。居留地を広げるのではなく、日本人と外国人とが隣り合わせで暮らす「雑居地」を設けるという考え方だ。
神木さんは強調した。「この雑居地の存在こそが神戸ならではの文化を育んでいきました」
しかも、特筆すべきことに、欧米人はトラブル防止のために設けた居留地の外に住んだにもかかわらず、内外の住民による大きな争いごとはなかったという。
北野付近に異人館が並んでいるのは偶然ではない。雑居地に指定された範囲だったため、欧米人が眺望の良い山麓に住み、居留地で貿易などのビジネスを行うようになったからだ。
「あくまで想像ですが、『おいしそうな食べ物やな』『おもろそうな遊びやな』みたいな住民のやりとりが頻繁にあり、互いの文化に合う形で取り込んでいったのではないでしょうか」
例えば、カステラと瓦せんべい。材料はほとんど同じだが、製法を変えることで洋菓子から和風の菓子が生まれた。これぞ雑居地のなせる技である。(安福直剛)
=随時掲載=
【バックナンバー】
(3)海軍操練所跡の碑 開港後は英国領事館に
(2)店のネーミング 「○番」-区画の名残
(1)150年変わらぬ町割り 道の名が日本の縮図