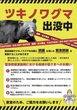2024年秋、精神的なダメージを受けて、ひどい吐き気やめまい、胃痛や頭痛に悩まされていた時期がある。会社を休み、長い時間をベッドで過ごした。その間、韓国人作家ハン・ガンの「別れを告げない」を読んでいた。読むことにも体力がいるから、本当に少しずつしか、読み進められなかった。でも、この小説のおかげで私はなんとか、苦しい時間を乗り越えることができた。
読むことそのものに痛みを感じる小説なのだが、それなのに引き寄せられ、離れられなかった。病院にも持っていき、待合室で読んでいた。
心の奥深いところに何かが届けられ、静かに私を癒やした。そんな力が、彼女の小説にはあると思う。
■歴史的トラウマ
アジア人女性初のノーベル文学賞を受賞したハン・ガンは「歴史的トラウマ」に立ち向かい、小説を紡いできたと評価された。「少年が来る」(2014年)と「別れを告げない」(21年)はその象徴であろう。
「少年が来る」は1980年の光州事件に材を取った。民主化運動に対する軍の弾圧である。「別れを告げない」は済州島の「4・3事件」を扱った。48年の島民の武装蜂起を契機に起きた国家権力による大量虐殺である。
この2作は密接につながっている。
「少年が来る」は受難者たちの側から歴史的悲劇を描く。
第1章「幼い鳥」に出てくる少年トンホは、遺体安置所で死臭に耐えながら犠牲者に寄り添っている。トンホは友人のチョンデとデモに加わり、チョンデが撃たれたときに置き去りにして逃げた。そのことをずっと引きずっている。
第2章「黒い吐息」は遺体となったチョンデの魂の視点で語られていく。
■生き残った恥辱
第3章「七つのビンタ」は出版社で働く女性編集者、遺体安置所でトンホとすれ違った人物が主人公となる。こんなくだりがある。
「黙々とご飯を咀嚼しながら彼女は思った。後ろ暗いところがある、食べるということには、と。なじんだ恥辱の中で彼女は亡くなった人たちのことを思った。あの人たちはもう永遠に空腹ではないのだ、生きていないのだから。でも彼女は生きていて空腹だった。この五年間、彼女を執拗に苦しめてきたことがまさにそれだった。空腹のせいで、食べ物に食欲をそそられること」
第4章「鉄と血」に出てくる文章も忘れられない。語り手は拷問を受けながらも生き延びた男性である。
「私は闘っています。日々一人で闘っています。生き残ったという、まだ生きているという恥辱と闘うのです」
1970年に光州で生まれたハン・ガンは80年1月、9歳のときに家族と一緒にソウルに引っ越す。光州事件の約4カ月前のことだ。そのわずかな運命の差異が、彼女と家族を虐殺される側から生き延びる側に移したと言ってもいいかもしれない。
そして12歳のときに、虐殺された市民の姿を写真集で見る。運命の無情と人間の残酷は、深く彼女の胸に刻まれただろう。まさしく彼女も「生き残った者」の一人なのだ。
■究極の愛の小説
「別れを告げない」の語り手「私」は作家自身を思わせる人物で、ある都市で起こった歴史的な惨劇についての小説を発表して間もないころ、という設定だ。拷問や虐殺のことを調べて書くうちに悪夢を見るようになり、偏頭痛や胃痙攣にも襲われ、立ち直れないでいる。
そんなとき友人のインソンから連絡が来る。彼女は大けがをしてソウルの病院に入院していた。インソンに頼まれて、「私」は済州島にあるインソンの家に向かう。
済州島出身のインソンは8年前に実家に戻り、4年も母の介護をして看取った。インソンの母は「4・3事件」の生き残りだった。事件の記憶に苦しみ、混乱し、「助けて」と訴える母との地獄のような日々。それなのにインソンは母の死後、事件の記録を調べ始めた。それはなぜだったのか-。
訳者の斎藤真理子によると、「別れを告げない」という題についてハン・ガンは「哀悼を終わらせない」という意味だと述べている。そして、この作品は「究極の愛の小説」だと説明したという。
踏みにじられる人の痛みや苦しみ、死者たちの無念、ついに果たされなかった夢や希望…。それらから目をそらさず、彼らの声に耳を傾け、生き残った者としての後ろめたさを抱えながら、想像し、共感し、共苦し続けること。それは、確かに「愛」である。
私たちは、どこまで人を愛することができるのか。ハン・ガンの作品を読んでいると、そんな重い問いを突きつけられる。
■魂の声響かせる
「ユリイカ」の2025年1月号はハン・ガン特集を組んでいる。詩人、森山恵の論考「舌が溶け、唇をほどく」は、詩から出発したハン・ガンという作家の核にあるものを、詩や小説の言葉から探り、こう結論付けている。
「個として踏み出した歩行は、『少年が来る』や『別れを告げない』において、歴史的暴力の記憶へと進んでいる。わたしたちが真の恢復に至るためには、文学的言語をとおして、激しい損傷の内部へと手を差し入れ、痛苦をともに身に引き受けること。自我を大きな空っぽの甕として、魂の声を響かせること。ハン・ガンの詩語は、そのようにわたしたちを啓いてゆく声である」
ハン・ガンの作品には、死者との回路が内包されている。読者は物語を読みながら、いつのまにか魂の声に耳を澄ませている。私もあの時期、その声を聴き取っていた。(敬称略/共同通信記者・田村文)
「少年が来る」の日本語版(井手俊作訳)は2016年にクオンから出版、「別れを告げない」の日本語版(斎藤真理子訳)は24年に白水社から出版された。