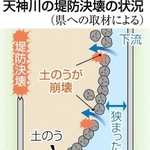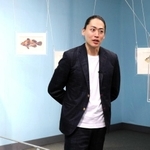■尼崎市の沖合 姫を奪われた武士の怨霊
見た人をおののかせるという伝承のカニは、現代にも実在していた。
「タケブンカニ」。兵庫県尼崎市の沖合に棲(す)むという妖怪で、鬼の顔をした甲羅を持ち、人に食べられることも少ない。それは怨霊の化身だからなのだろうか-。
鎌倉時代末期、倒幕に失敗した後醍醐天皇の家臣・秦武文(はたのたけぶん)は、土佐に流された皇子に姫を会わせるべく、姫のお供として京都を発(た)つと、尼崎の港で海賊に襲われる。姫を奪われた武文は腹を切って海へ飛び込み、怨霊となって嵐を呼んで姫を助けたという。
これは南北朝の内乱を描いた「太平記」の一場面だ。時は下って江戸時代、武文の怨霊がカニとなって尼崎の沖にいる-との紀行文や地誌が出回った。
「おそらくヘイケガニ科のカニのことですね」と、同県西宮市貝類館の学芸員渡部哲也さん(49)が指摘する。現物の写真を見ると、確かに目がつり上がり、歯を食いしばるような憤怒の人相が甲羅に浮かんでいる。
ヘイケガニは源平合戦で敗れた平家の怨念で生まれたといわれ、正式な学術名にもなっている。戦後、世界的にも注目され「日本人は平家の亡霊と恐れて食べないため、種の保護につながった可能性がある」とする英国学者の論文が論争を巻き起こしたこともある。
これに対して渡部さんは「単純に食べるところがないだけ」と笑う。浅い海底に生息し、底引き網に10匹以上も混ざることがあるが、そもそも甲羅は幅2~3センチで肉が少なく、食用には適さないという。
つまりタケブンカニとは、ヘイケガニ科のカニの異名らしい。ちなみに尼崎ではこのカニをタケブンカニと呼ぶ人は少なく、昭和初期に「尼崎今昔物語」を記した地元教員の畠田繁太郎は「我々(われわれ)は事実、そんな名前を以(もっ)てあの蟹を呼んだことはない」と記している。
市南部にある善通寺には、武文のものと伝わる墓が残る。史料が少なく実在したかどうか分からない人物だが、住職の海老原学善さん(48)は言った。
「武文は忠義を尽くして姫を助けた、まじめな武士だったと地元に伝わっています。カニの妖怪だなんて…、私たちにそんな印象はありません」
【メモ】ヘイケガニ科は大阪湾や瀬戸内海にヘイケガニやサメハダヘイケガニ、キメンガニがいる。尼崎では他に、戦国時代に敗死した島村貴則が生まれ変わったとされる「シマムラカニ」、愛知県では源頼朝に処刑された長田忠致(おさだただむね)にちなむ「オサダガニ」などと各地で悲劇の人物と重ねられる。武文は室町時代の御伽草子や演舞に取り入れられて知られるようになった。

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
三田阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化神戸阪神

-
阪神地方行政

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
スポーツ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神スポーツストークス

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神明石神戸

-
阪神地方行政

-
おくやみ阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
文化阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神

-
新型コロナ姫路阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神タカラヅカ

-
阪神

-
阪神スポーツバレー

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
教育阪神

-
阪神

-
阪神#インスタ

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神バスケ

-
阪神

-
阪神選挙

-
阪神岡崎慎司×兵庫

-
阪神

-
阪神

-
阪神地方行政

-
阪神連載阪神

-
阪神

-
選挙神戸阪神

-
阪神

-
LGBT阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
阪神

-
神戸阪神明石淡路

-
淡路阪神神戸東播姫路

-
阪神

-
阪神