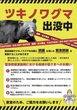生き物が関わるイベントでは、「生き物を野外に逃がしてはいけません」と指導されることが多くなってきました。そもそも、なぜ生き物を野外に逃がしては駄目なんでしょう。今回はその理由について詳しく紹介します。
まずは、逃がした生き物が外来生物だった場合です。アメリカザリガニやホテイアオイなど、一部の外来生物は野外に定着するとどんどん数を増やしてしまい、その自然環境に元々すんでいた在来種がすめない環境となってしまいます。
特に「日本の侵略的外来種ワースト100」に掲載されている外来生物は生態系への被害が大きいことが知られており、また外来生物の中には、野外に生きたまま逃がすことが外来生物法で禁止されている種類もいます。
次に、在来種ではあるものの、遠い地域から連れてきた生き物の場合です。メダカだったら日本のどこにでもいるから大丈夫じゃないの、と思うかもしれませんが、実はこれも日本各地で問題になっている行為です。
メダカをはじめ、日本の在来種は多くの場合、地域ごとに異なる遺伝子を持っています。遠くから人間によって運ばれた個体と、元々の在来個体が交雑することで、本来と異なる遺伝子の構造となってしまうことを「遺伝的撹乱(かくらん)」と呼びます。
2017年の近畿大学の研究では、日本のメダカについて調べた地点のおよそ半数で遺伝的撹乱が起きていたことが分かっています。こうしたことを防ぐために、たとえ在来種でも遠くの地域のものを逃がすのはお勧めできません。
最後に、取ってきた場所に逃がす場合はどうでしょうか。上記2点より影響は小さいのですが、実はこれもあまりお勧めできません。人間の飼育・栽培環境には、野外ではいない病原体や寄生虫がすんでいるリスクがあります。こうした病原体や寄生虫をむやみに広めないためにも、たとえ同じ場所の生き物でも、一度飼育したら野外に逃がさないに越したことはありません。
あれも駄目これも駄目な話になってしまい恐縮ですが、それはやはり生き物を逃がす行為の影響が非常に大きいためです。ペットや園芸植物の場合は、最後まで飼育栽培する気持ちで臨むことが大事ですし、保全目的で生き物を野外に放す場合でも、まずは専門家に相談していただくのがよいでしょう。